|
第34回 エッセンの屋久杉
2013年11月1日
 外国に住んでいると、意外なところで日本と御縁の深い方に出会ったり、日本文化と深い関わりのある物品や施設を発見したりします。このコラムでもたびたび御紹介しているように地方自治体や民間ベースでの日白交流も一般に想像される以上にすすんでいます。しかし、今回、ブリュッセルの北90km、オランダと国境を接するエッセンという小さな村に住むベルギー人の友人宅に招かれて屋久杉の林を見た時ほど驚いたことはありません。日本列島の南端近くに位置する屋久島はユネスコの世界遺産に指定された樹齢1千年を超えるスギの樹林で有名ですが、このエッセンの友人宅には40年ほど前に屋久杉の株が移植され、現在、60本ほどの「小杉」が育っています。気候風土の違いから生育が遅いようですが、もともと屋久杉は栄養の少ない花崗岩の上に育つために成長が遅く、その結果として樹齢が極めて長くなるのが特長です。100ヘクタール(1km×1km)もある広大な庭園には両親の代にいろいろな日本の樹木が植えられているのですが、その中でも屋久杉の樹林はひときわ目立っており、1千年後に(?)大木に育っていれば素晴らしいことだと思います。 外国に住んでいると、意外なところで日本と御縁の深い方に出会ったり、日本文化と深い関わりのある物品や施設を発見したりします。このコラムでもたびたび御紹介しているように地方自治体や民間ベースでの日白交流も一般に想像される以上にすすんでいます。しかし、今回、ブリュッセルの北90km、オランダと国境を接するエッセンという小さな村に住むベルギー人の友人宅に招かれて屋久杉の林を見た時ほど驚いたことはありません。日本列島の南端近くに位置する屋久島はユネスコの世界遺産に指定された樹齢1千年を超えるスギの樹林で有名ですが、このエッセンの友人宅には40年ほど前に屋久杉の株が移植され、現在、60本ほどの「小杉」が育っています。気候風土の違いから生育が遅いようですが、もともと屋久杉は栄養の少ない花崗岩の上に育つために成長が遅く、その結果として樹齢が極めて長くなるのが特長です。100ヘクタール(1km×1km)もある広大な庭園には両親の代にいろいろな日本の樹木が植えられているのですが、その中でも屋久杉の樹林はひときわ目立っており、1千年後に(?)大木に育っていれば素晴らしいことだと思います。
<ベルギー連邦議会の対日友好議員連盟>
  各国の議会には個々の外国との友好関係促進を目的とした友好議員連盟という組織があります。ベルギーの連邦議会の場合はこうした友好議員連盟が大変良く組織されており、日本を含む世界のほとんどの国毎に議員グループが存在します。日本との友好議員連盟の会長は、前任のトルフス上院議員がルーヴァン・カトリック大学(KUL)の学長に転出したため、最近新たにシュープ上院議員が就任しました。私は、10日ほど前に新会長を表敬訪問し、懇談する機会を得ました。シュープ議員は開口一番「私は政治家ではありません」とおっしゃられて私を驚かせたのですが、事実、同議員は長らく鉄道分野で要職を務めており、ベルギー国鉄の総裁や国際鉄道連盟の会長などを歴任しています。20年ほど前にJR東日本の招待で日本を訪問したこともあるとのことでした。今回の表敬には副会長のシルツ下院議員も同席してくれました。シルツ議員は弁護士の資格を有する34歳の若き政治家ですが、父親がかつて副首相を務め、本人も既に6年以上の議員歴を有するとのお話には驚きました。現在、下院の原子力安全小委員会の委員長職にあり、福島の原発事故には強い関心を持っているとのことでした。このように、ベルギー側の対日友好議連の体制が整っているのは大変嬉しいのですが、問題は、日本側の対ベルギー友好議連の組織が曖昧になっていることです。早期に日本側でも体制が整備され、大いに議員交流を進めて欲しいところです。 各国の議会には個々の外国との友好関係促進を目的とした友好議員連盟という組織があります。ベルギーの連邦議会の場合はこうした友好議員連盟が大変良く組織されており、日本を含む世界のほとんどの国毎に議員グループが存在します。日本との友好議員連盟の会長は、前任のトルフス上院議員がルーヴァン・カトリック大学(KUL)の学長に転出したため、最近新たにシュープ上院議員が就任しました。私は、10日ほど前に新会長を表敬訪問し、懇談する機会を得ました。シュープ議員は開口一番「私は政治家ではありません」とおっしゃられて私を驚かせたのですが、事実、同議員は長らく鉄道分野で要職を務めており、ベルギー国鉄の総裁や国際鉄道連盟の会長などを歴任しています。20年ほど前にJR東日本の招待で日本を訪問したこともあるとのことでした。今回の表敬には副会長のシルツ下院議員も同席してくれました。シルツ議員は弁護士の資格を有する34歳の若き政治家ですが、父親がかつて副首相を務め、本人も既に6年以上の議員歴を有するとのお話には驚きました。現在、下院の原子力安全小委員会の委員長職にあり、福島の原発事故には強い関心を持っているとのことでした。このように、ベルギー側の対日友好議連の体制が整っているのは大変嬉しいのですが、問題は、日本側の対ベルギー友好議連の組織が曖昧になっていることです。早期に日本側でも体制が整備され、大いに議員交流を進めて欲しいところです。
<最も広く、最も人口の少ないルクセンブルグ州>
 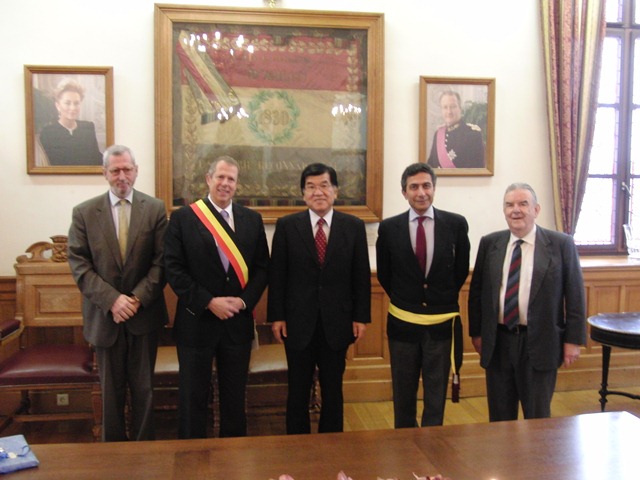 先週、ベルギーの南東の端に位置し、面積が最も広いのに(4440k㎡)人口は最も少ない(27万人)ルクセンブルグ州を公式訪問しました。ブリュッセルからおよそ190km、車で2時間近くかかる州都アルロン市の人口は何と28000人、ベルギー10州の州都の中でも最も小さな町です。ルクセンブルグ州が誕生したのは1839年で、ベルギー独立の9年後になります。隣接するルクセンブルク大公国から分離されてベルギー側に編入されたのですが、この間の歴史は相当に複雑なようです。過去18年間に亘って現職にあるカプラス州知事によれば、長いこと「農業と林業の国」と言われたルクセンブルグ州も近年は「先端産業が集積する国」に次第に変貌しつつあり、ベルギーでも豊かな州の1つとして認知されているとのことです。フランスとも国境を接していることから、フランス側に居住しながらルクセンブルグ州で働いているフランス人が6千人いるとのことですが、他方でルクセンブルグ州に居住しながらルクセンブルク大公国側で働く州民も3万人いる由です。興味深いのは、フランス人は居住地のフランス側で所得税を支払っているのに、ルクセンブルグ州民は勤務先のルクセンブルク大公国側で支払っているとのお話でした。ベルギー側の税金が高いのが一因のようです。このため、ルクセンブルグ州はルクセンブルク大公国との取り決めによって州民が支払っている所得税の一部について還付を受けているとのことです。州都のアルロン市については、マグヌス市長などによれば、チェチェン人など外国からの移住者が増えており、出身地や宗教が異なる市民の間の融和が1つの課題になっているとのことでした。これらの会見には引退後アルロン市近郊に居を構えておられるパトリック・ノートン元駐日大使が同席してくれました。 先週、ベルギーの南東の端に位置し、面積が最も広いのに(4440k㎡)人口は最も少ない(27万人)ルクセンブルグ州を公式訪問しました。ブリュッセルからおよそ190km、車で2時間近くかかる州都アルロン市の人口は何と28000人、ベルギー10州の州都の中でも最も小さな町です。ルクセンブルグ州が誕生したのは1839年で、ベルギー独立の9年後になります。隣接するルクセンブルク大公国から分離されてベルギー側に編入されたのですが、この間の歴史は相当に複雑なようです。過去18年間に亘って現職にあるカプラス州知事によれば、長いこと「農業と林業の国」と言われたルクセンブルグ州も近年は「先端産業が集積する国」に次第に変貌しつつあり、ベルギーでも豊かな州の1つとして認知されているとのことです。フランスとも国境を接していることから、フランス側に居住しながらルクセンブルグ州で働いているフランス人が6千人いるとのことですが、他方でルクセンブルグ州に居住しながらルクセンブルク大公国側で働く州民も3万人いる由です。興味深いのは、フランス人は居住地のフランス側で所得税を支払っているのに、ルクセンブルグ州民は勤務先のルクセンブルク大公国側で支払っているとのお話でした。ベルギー側の税金が高いのが一因のようです。このため、ルクセンブルグ州はルクセンブルク大公国との取り決めによって州民が支払っている所得税の一部について還付を受けているとのことです。州都のアルロン市については、マグヌス市長などによれば、チェチェン人など外国からの移住者が増えており、出身地や宗教が異なる市民の間の融和が1つの課題になっているとのことでした。これらの会見には引退後アルロン市近郊に居を構えておられるパトリック・ノートン元駐日大使が同席してくれました。
<ナミュール州知事と過ごした半日>
  先日、ナミュール州のマッテン州知事から招待を受け、同州の企業訪問や企業関係者との懇談、昼食会に臨み、そして最後には美術館も訪問して、ほぼ半日を州知事と御一緒に過ごしました。最初に訪問した企業はBEALという漆喰製造会社で、社員数18名という極めて小さな会社です。40年近い社歴を有する家族経営の会社なのですが、「モルテックス」という製品を海外にも輸出しており、是非日本にも販路を拡げたいとの意欲に燃えておりました。私が訪問した日には住宅の特殊工事を請け負う東京の会社の社長や淡路島から来たという左官職人の方も同席されて、「モルテックス」が優れた防水性と付着性を有することを高く評価しておりました。その後、州知事の庁舎で行われた企業関係者との懇談では、看板製作からネット広告、ビール製造までさまざまな業種の企業家とお会いしたのですが、興味深かったのは心臓動脈瘤の治療に使うステントを製造している「カルディアティス」という会社で、社歴10年ながら40人の社員を雇用し、欧州各国や北米まで製品を輸出しているとのことです。日本企業との連携を模索しており、そのために今年から日本人の弁理士まで採用しているようです。最後の美術館訪問は、私の強い希望で、金銀細工品で有名なヒューゴ・ドワニーの作品群を見学させてもらいました。13世紀初頭に製作された金銀細工品の豪華さと精巧さは誠に驚くべきもので、ベルギーの「7つの秘宝」の1つに数えられているようです。過去に何度も盗難の危険に遭遇し、その都度、近隣の教会や修道院の地下に秘蔵されて来たとの説明でした。ミューズ川とサンブル川が合流する地点に発達したナミュール市の風景は実に美しく、今や私にとって「お気に入りの町」の1つになっています。 先日、ナミュール州のマッテン州知事から招待を受け、同州の企業訪問や企業関係者との懇談、昼食会に臨み、そして最後には美術館も訪問して、ほぼ半日を州知事と御一緒に過ごしました。最初に訪問した企業はBEALという漆喰製造会社で、社員数18名という極めて小さな会社です。40年近い社歴を有する家族経営の会社なのですが、「モルテックス」という製品を海外にも輸出しており、是非日本にも販路を拡げたいとの意欲に燃えておりました。私が訪問した日には住宅の特殊工事を請け負う東京の会社の社長や淡路島から来たという左官職人の方も同席されて、「モルテックス」が優れた防水性と付着性を有することを高く評価しておりました。その後、州知事の庁舎で行われた企業関係者との懇談では、看板製作からネット広告、ビール製造までさまざまな業種の企業家とお会いしたのですが、興味深かったのは心臓動脈瘤の治療に使うステントを製造している「カルディアティス」という会社で、社歴10年ながら40人の社員を雇用し、欧州各国や北米まで製品を輸出しているとのことです。日本企業との連携を模索しており、そのために今年から日本人の弁理士まで採用しているようです。最後の美術館訪問は、私の強い希望で、金銀細工品で有名なヒューゴ・ドワニーの作品群を見学させてもらいました。13世紀初頭に製作された金銀細工品の豪華さと精巧さは誠に驚くべきもので、ベルギーの「7つの秘宝」の1つに数えられているようです。過去に何度も盗難の危険に遭遇し、その都度、近隣の教会や修道院の地下に秘蔵されて来たとの説明でした。ミューズ川とサンブル川が合流する地点に発達したナミュール市の風景は実に美しく、今や私にとって「お気に入りの町」の1つになっています。
<アントワープ大学での講演>
 先日、初めてアントワープ大学を訪問し、100人ほどの学生を前に「現在の日本とその将来」というテーマで講演しました。学生の大半は修士課程の学生のようでしたが、担当の助教授の事前説明では日本に関する学生の知識は極めて乏しいとのことでしたので、出来る限り分かりやすくお話をするように努めました。私は、講演の冒頭で、1620年にアントワープ出身のイエズス会士がキリスト教布教のために日本を訪れた歴史に触れ、その後、(この日の午後に日本映画「3丁目の夕日」の上映を予定していた関係で)1960年頃の日本人の生活について説明しました。現在64~67歳になる日本人(いわゆる「団塊の世代」)にとっては誠に懐かしい「古き良き時代」なのですが、1960年前後は戦後の復興期が終わりつつあり、高度成長期に移る直前の時期に相当します。日本全体は未だ貧しいのですが、人々の結びつきは強く希望に満ちてきた時代ですね。しかし、その後、20年近い高度成長期を経てバブルが崩壊し、今日まで続く長い経済低迷期を迎えることになります。物質中心の時代にあって貧富の格差は広がり、漠然とした不満がうっ積します。社会の高齢化も進み、年金制度の維持も難しくなって行きます。こうした中で、昨年末に安倍政権が誕生し、「アベノミックス」と呼ばれる経済政策をはじめ次々と新たな政策を打ち出し、日本社会に少し活気が出てきたように感じられます。私は、最後に、日本の将来に関わる問題点として長期のエネルギー政策や高齢化社会への取り組みなどについて説明したのですが、果たして学生諸君の理解が得られたのか余り自信はありません。 先日、初めてアントワープ大学を訪問し、100人ほどの学生を前に「現在の日本とその将来」というテーマで講演しました。学生の大半は修士課程の学生のようでしたが、担当の助教授の事前説明では日本に関する学生の知識は極めて乏しいとのことでしたので、出来る限り分かりやすくお話をするように努めました。私は、講演の冒頭で、1620年にアントワープ出身のイエズス会士がキリスト教布教のために日本を訪れた歴史に触れ、その後、(この日の午後に日本映画「3丁目の夕日」の上映を予定していた関係で)1960年頃の日本人の生活について説明しました。現在64~67歳になる日本人(いわゆる「団塊の世代」)にとっては誠に懐かしい「古き良き時代」なのですが、1960年前後は戦後の復興期が終わりつつあり、高度成長期に移る直前の時期に相当します。日本全体は未だ貧しいのですが、人々の結びつきは強く希望に満ちてきた時代ですね。しかし、その後、20年近い高度成長期を経てバブルが崩壊し、今日まで続く長い経済低迷期を迎えることになります。物質中心の時代にあって貧富の格差は広がり、漠然とした不満がうっ積します。社会の高齢化も進み、年金制度の維持も難しくなって行きます。こうした中で、昨年末に安倍政権が誕生し、「アベノミックス」と呼ばれる経済政策をはじめ次々と新たな政策を打ち出し、日本社会に少し活気が出てきたように感じられます。私は、最後に、日本の将来に関わる問題点として長期のエネルギー政策や高齢化社会への取り組みなどについて説明したのですが、果たして学生諸君の理解が得られたのか余り自信はありません。
<日本人画家の個展>
 現在、ヘレンタル市(ブリュッセルの北東70km:人口27000人)にある美術館において、日本人画家の作品展が開催されています。画家は有森正と言い、5年ほど前からトゥールネ市(ブリュッセルの南西85km)に在住して、抽象的な作品を多く手掛けておられます。私は、10日ほど前に開催された内覧会に招待され、60点近い作品群を鑑賞させていただきました。元々粉を挽くための風車小屋だった建物を近代的な内外装に全面改修したという美術館は、有森さんの作品と大変マッチしておりました。どの作品にもデッサンらしいものはなく、その意味では絵画というよりも黄金色と濃紺や茶褐色を基調とした色彩の組み合わせを楽しむような作品なのですが、じっと眺めていると妙に心が安らぐような感じが得られました。有森さんを私に紹介してくれたのはワロン地域政府のデモット首相の奥様で、日本に強い関心をお持ちのようです。この日の内覧会には、平日の夜、しかも地方都市で開催されたイベントにもかかわらず絵画の愛好家を中心に100名ほどが出席しておりました。展覧会は12月まで続くようですから、是非多くの方に見て欲しいと思います。 現在、ヘレンタル市(ブリュッセルの北東70km:人口27000人)にある美術館において、日本人画家の作品展が開催されています。画家は有森正と言い、5年ほど前からトゥールネ市(ブリュッセルの南西85km)に在住して、抽象的な作品を多く手掛けておられます。私は、10日ほど前に開催された内覧会に招待され、60点近い作品群を鑑賞させていただきました。元々粉を挽くための風車小屋だった建物を近代的な内外装に全面改修したという美術館は、有森さんの作品と大変マッチしておりました。どの作品にもデッサンらしいものはなく、その意味では絵画というよりも黄金色と濃紺や茶褐色を基調とした色彩の組み合わせを楽しむような作品なのですが、じっと眺めていると妙に心が安らぐような感じが得られました。有森さんを私に紹介してくれたのはワロン地域政府のデモット首相の奥様で、日本に強い関心をお持ちのようです。この日の内覧会には、平日の夜、しかも地方都市で開催されたイベントにもかかわらず絵画の愛好家を中心に100名ほどが出席しておりました。展覧会は12月まで続くようですから、是非多くの方に見て欲しいと思います。
| 