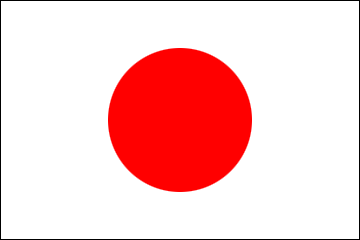ベルギーと私
ベルギーと私
栗田路子
|
今日も電話が鳴る。「日本の制作会社です。ベルギーロケをしたいのですが…」また、仕事の依頼だ。「ここは、暗くジメジメしてパッとしないし、人件費が高いから費用が嵩むし、アジアとかアメリカとか南欧に行かれることをお奨めしますが…」と応える。ところが最近こんなことを言われてしまった「でもベルギーは、日本人の『行ってみたい欧州の国トップ10』に入るんですよ。それも、栗田さんのセイだって噂も。」人聞きが悪い。でも、日本にベルギーを紹介する仕事に携わって来たものにとっては、ちょっぴり嬉しい。 前夫に先立たれ、環境全取替えをもくろんでアメリカ留学を着々と進めていたある日、目の前に現れた欧州人にこう言われた。「アメリカと日本だけが世界の中心じゃないよ。一度、ヨーロッパも見たら?」始めて渡った欧州の国はなんと『ベルギー』。そこでアキレス腱を全断するアクシデントに遭い、片言すらおぼつかない仏語の世界で、全身麻酔の手術を受けることになった。これがベルギーと私の腐れ縁の始まり。 あまりにもいろいろなことがあった。松葉杖と石膏姿で始まった私の米国留学は、「胸部レントゲンに結核らしい影がある」との理由で、継続不可能となり、アキレス腱の一件で助けてくれた今の夫が「それならベルギーで続ければ」と『プロポーズ』してくれたおかげで、ルーヴァン・カトリック大学(KUL)のビジネススクールで完了した。さて何をしようかと考えたとき、ベルギービールの日本向け輸出マーケティングを思いついた。大学卒業後に勤務した外資系広告代理店では、ネッスレだの、ロレアルだのといった、国際銘柄の消費財マーケティングに携わっていたからだ。ちょうど、ベルギービールで新規ビジネスを構築しようとしていた小西酒造(在伊丹市)の社長と知り合い、ベルギービールの日本市場開拓に没頭した。20年前には「ベルギー?知らないなあ。旧東欧? もったりしたビールは日本人の口には合わないから無理だよ」と冷たくあしらわれてばかりいたので、最近になって「ベルギービール?白ビールやトラピストはいいね。また日本に新しいベルギービール店ができたよ」などと言われると、先駆者冥利で密かにほくそえんでしまう。小西酒造さんとのお仕事は2008年で終止符を打ったが、今でも日本でベルギービール新店舗オープンなどがあると、単発でお手伝いしている。20年の『輸出貢献』をどなたかがアピールして下さり、グランプラスにある『ベルギービール醸造家組合』から、その『名誉騎士』に加えていただいた。光栄に思っている。 その間、私生活面では、ベルギーという不思議な国の、『意外に』進んだ医療制度や人権意識の恩恵をひたすら享受してきたように思う。子宝に恵まれなかった私達は、医療保険でカバーされる先端生殖医療の粋を尽くした不妊治療を受けさせてもらった。でも、その途中、ふと思った。「血のつながり」にこだわるよりも、生まれてしまっている子を育てる方が、自分の性に合っている。その選択肢がこの国にはあるのだと。厳しい審査と待機時間を経て、ベトナムに渡り、ようやく手にしたわが子は、重度心身障害児だった。このときの苦境を私達と供に歩いてくれたのも、この国のごく普通の人々だった。日本国籍の私が、自ら望んでベトナムから養子に迎えた子が、障害児だったからといって、この国の人たちが長年かけて作り上げてきたギリギリの社会保障制度のお荷物になって良いものか。そんなとき幾度となく、まわりの普通のベルギー人に「どんな子どもであっても社会の宝」「昼間は介護を職業とする人々に任せて、お母さんは仕事や趣味で自分らしく生きるべき」「この子の面倒をみさせてくれてありがとう」などと言われ、その懐の深さに言葉を失ったものだ。障害や病気を持つ孤児の養子縁組を推進する殊勝な人々と出遭い、彼らを資金援助するチャリティ基金『ネロとパトラッシュ基金』 i を設立して運営することで、かろうじて少しだけ恩返しをしようと奮闘した。 2004年・2008年と乳がんを患い、がむしゃら人生を一時休止。違う生き方を模索しようとして始めたのが、この不思議な国ベルギーと人々を日本に向けて紹介し、発信していくことだった。日本のテレビ・雑誌などの海外取材は、『コーディネータ』なる現地の『何でも屋』によって成立している。現地コーディネータは、下請けの下請けだから、まるで奴隷のように時間制限なくこき使われ、魔法使いのように何でもできて当然で、できなければ叱責される。パリやロンドンなどの大都市なら星の数ほどもいる専業のコーディネータは、ベルギーにはほどんどいない。公用語三言語と英語のうちのいくつかを操ることができ、どの地域にも広いトリビア的情報と人的ネットワークを持ち、何を言われてもへこたれない精神力と体力を持つ日本人は希だ。ワーホリ制度もなく、言語学校ではビザが出ないベルギーには、こういうハードな仕事を喜んで引き受ける、若く元気な人材も乏しい。バイトも、フリーターも許されないので、こういう単発仕事を日本の相場で引き受けることがでる受け皿がいないのだ。そこで、観光ガイドなどをしている自営業の方々と、『コーディネーターズ・クラブ・ベルギー』 ii というグループを結成して、分担して仕事を引き受けるように工夫している。今では、月に1~3本の番組をこなすようになり、日本で放映されるベルギー関連番組のほとんどに関与していると言えると思う。表面的なバラエティ番組がほとんどだが、こうして、この国の歴史や社会事情を知り、人々に出会う機会に恵まれる。それを資本に、自らもプレスパスを取り、細々ながら、朝日新聞のWEBRONZA iii などいくつかの媒体に書くことでも発信している iv 。 ベルギーに渡って20年余り。仕事を通して、また、数奇な運命(?)のおかげで、普通のサラリーマンや主婦なら知りえないこの国と人々の、不思議さにも、人権意識の奥深さにも接した。たとえば、地雷廃止の国連条約に最初に批准したのがこの国であったことも、世界トップクラスの臓器移植水準を誇り、それが健康保険の枠内で実施されていることも知った。ベルギーでは、「夫婦別姓」はごく自然に定着して今や話題にもならないし、「非正規社員」なぞ存在せず、額は別として「失業保険の受給期間」は無限だ。複数党連立政権樹立が難航して政府不在が1年以上に渡っても、国民は落ち着いて平和に暮らしているし、カトリック国であるにも関わらず「同性結婚」も「安楽死」もいち早く合法化してしまう。最近、ゲイについての取材で、ベルギーやブリュッセル政府が、「ゲイ・フレンドリー・キャンペーン」によって、人種、国籍、性別、出自、性的志向等、属性や特徴によって、人を中傷したり差別したりせず、誰もが自分らしく生きる権利を推進していると聞いて、心底共鳴してしまった。この国の不便さや非効率を割り引いても、私がここで居心地が良いと感じるのは、自分がどんな少数派側に転がっても、大勢から切り捨てられることなく、その権利と平等を守ろうとする市民の強い絆があると実感するからなのだと思う。 もちろん、国は今にも崩壊寸前で、人々は時間にルーズでサービス精神に欠け、特有の「ベルギー的妥協」に直面するとうんざりするのは日常茶飯事だ。この国に長く生きる日本人盟友の中には、「老後は絶対に日本」と決めている人もいる。ある日、「貴女、ベルギーに骨を埋める覚悟をしたの?」と真面目顔で聞かれた。「安楽死」も「臓器の積極提供」も届け出てしまった私は、もうとっくに、ベルギーに半身埋まってしまっているようなもの。それに、この国は、私の命あるうちに平和裏に消滅してしまっているかもしれないから、『ベルギー』にこだわるつもりもなく、むしろ残された家族に都合の良いように散骨なり何なりしてくれればいいと思っている。いずれ、この地球のどこかに返るのだから。 i 2013年に正式終了 www.multilines.be/np |