
第58回 ベルギーの富豪たち
2014年7月11日
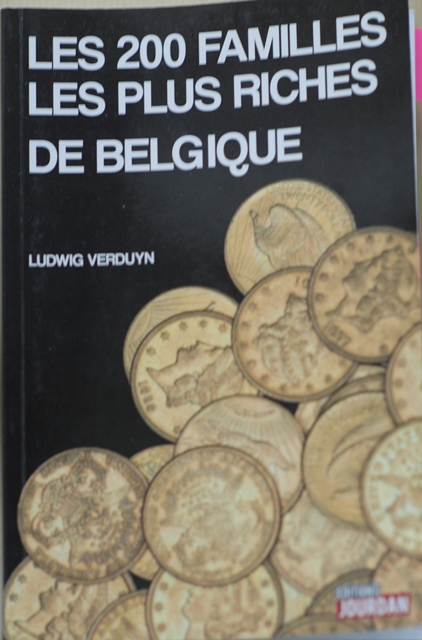 先日、近所の書店で「ベルギーの金満一族200」という本を偶然見つけ衝動買いしました。以前、米国の調査会社が「億万長者がたくさん住んでいる国ランキング」(2013年)というのを発表していて、ベルギーは世界で12位(日本は11位)、ヨーロッパだけではスイスに次いで第2位という結果だったと記憶しています。因みに、「生活費の高い国ランキング」というのもあって、こちらではベルギーは世界8位(日本は第6位)でした。フォーブスが毎年発表している「世界の長者番付」の最新版によると、ベルギー第1位の金持ちはアルベール・フレールという銀行家(88歳)で、資産総額49億ドル、世界で295位にランクされています。ところが、冒頭に述べた書物によれば、フレール一族はベルギー国内で18番目にランクされており、個人単位と家族単位で所有資産を比較しているという違いはあるものの、やや意外な内容でした。このベルギー人の書いた書物で第1位にランクされている一族(ファミリー)はヤンセン家で、化学・製薬企業から主要銀行までを傘下に収める大実業家です。現在の当主はニコラ・ヤンセン氏で、その夫人はマティルド王妃の姉君に当たる女性ですので、ベルギー王家とも結びついています。まあ、納得のランキングです。ところが、ここに謎の人物が登場します。数年前まではアルベール・フレール氏を上回る大金持ちと言われたパトフ・チョディエフ氏がその人物で、確かにベルギー国籍を取得しているのですが、ウズベキスタンに生まれ、現在はカザフスタンに在住しているようです。若き日にモスクワで日本語を学び、東欧やアフリカで鉱山開発事業を始めるまでは日本に住んでいたという不思議な経歴の持ち主です。フォーブスの世界長者番付では4年前に世界287位にランクされたこともありますが、今年の最新版では資産総額19億ドルで、962位まで下落しました。脱税やマフィアとの繋がりなどとかくの噂のある人物らしく、ベルギー人の書いたランキング本の中では無視されています。まあ、世界にはいろいろな富豪がいるようですね・・・。 先日、近所の書店で「ベルギーの金満一族200」という本を偶然見つけ衝動買いしました。以前、米国の調査会社が「億万長者がたくさん住んでいる国ランキング」(2013年)というのを発表していて、ベルギーは世界で12位(日本は11位)、ヨーロッパだけではスイスに次いで第2位という結果だったと記憶しています。因みに、「生活費の高い国ランキング」というのもあって、こちらではベルギーは世界8位(日本は第6位)でした。フォーブスが毎年発表している「世界の長者番付」の最新版によると、ベルギー第1位の金持ちはアルベール・フレールという銀行家(88歳)で、資産総額49億ドル、世界で295位にランクされています。ところが、冒頭に述べた書物によれば、フレール一族はベルギー国内で18番目にランクされており、個人単位と家族単位で所有資産を比較しているという違いはあるものの、やや意外な内容でした。このベルギー人の書いた書物で第1位にランクされている一族(ファミリー)はヤンセン家で、化学・製薬企業から主要銀行までを傘下に収める大実業家です。現在の当主はニコラ・ヤンセン氏で、その夫人はマティルド王妃の姉君に当たる女性ですので、ベルギー王家とも結びついています。まあ、納得のランキングです。ところが、ここに謎の人物が登場します。数年前まではアルベール・フレール氏を上回る大金持ちと言われたパトフ・チョディエフ氏がその人物で、確かにベルギー国籍を取得しているのですが、ウズベキスタンに生まれ、現在はカザフスタンに在住しているようです。若き日にモスクワで日本語を学び、東欧やアフリカで鉱山開発事業を始めるまでは日本に住んでいたという不思議な経歴の持ち主です。フォーブスの世界長者番付では4年前に世界287位にランクされたこともありますが、今年の最新版では資産総額19億ドルで、962位まで下落しました。脱税やマフィアとの繋がりなどとかくの噂のある人物らしく、ベルギー人の書いたランキング本の中では無視されています。まあ、世界にはいろいろな富豪がいるようですね・・・。
<スパは水と鉱泉の町>
  「スパ」と言えば日本でも外国でも温泉・湯治場を意味する一般名詞なのですが、ベルギーだけは事情が異なります。ブリュッセルから南東に140kmほど離れたところに、「スパ」という町(人口10500人)があり、そこが鉱泉場になっていますので「スパ」は固有名詞なのです。また、ベルギーでは、その名も「スパ」というミネラルウォーターが広く飲まれていますが、これは「スパ」の町周辺を水源として大量に生産されている飲料水です。つまり、ベルギーでは「スパ」は水と鉱泉の町であり、これが世界的に知られるに及んで、「スパ」が温泉・湯治場を意味する一般名詞になったというのが通説のようです。 「スパ」と言えば日本でも外国でも温泉・湯治場を意味する一般名詞なのですが、ベルギーだけは事情が異なります。ブリュッセルから南東に140kmほど離れたところに、「スパ」という町(人口10500人)があり、そこが鉱泉場になっていますので「スパ」は固有名詞なのです。また、ベルギーでは、その名も「スパ」というミネラルウォーターが広く飲まれていますが、これは「スパ」の町周辺を水源として大量に生産されている飲料水です。つまり、ベルギーでは「スパ」は水と鉱泉の町であり、これが世界的に知られるに及んで、「スパ」が温泉・湯治場を意味する一般名詞になったというのが通説のようです。
 さて、私は、先週、ミネラルウォーター「スパ」を生産しているスパデル社のデュボア社長から招待を受け、生産現場を視察する機会を得ました。正確に申し上げると、スパデル社は統括会社で、ベルギーの2か所の他、フランス、英国でもミネラルウォーターの生産をしており、「スパ」の町にある工場は「スパ・モノポール」という名前の子会社です。スパ・モノポール社は13000haの広大な敷地(高原地帯)に42の水源を有し、地下20~200mを流れる自然水を無処理でボトル詰めしているとのことです。町の中心部に位置する工場は完全に自動化された設備を有しており、1時間に4万本のペースでボトル詰めの作業が行われている風景は圧巻でした。デュボア社長によればスパの町でミネラルウォーターが採取され、海外に輸出されるようになったのは1583年だそうですが、現在のスパ・モノポール社が設立されたのは今から100年ほど前の1912年であり、その後、1920年代にこの会社をデュボア社長の祖父が取得し、以来、この会社はデュボア一族が経営しているとのことでした。スパの地下水はミネラル成分や塩分が少なく飲みやすい(乳幼児向き?)のが特徴であり、また炭酸の量も少ないので炭酸水の場合は炭酸を加えているようです。スパデル社の年間売上額は210百万ユーロ(約300億円)で、ミネラルウォーターの販売会社としてはヨーロッパでは14~15番目の中堅企業です。日本への輸出は1990年代に具体的な取引話があったものの、未だ実現していないとのことでした。 さて、私は、先週、ミネラルウォーター「スパ」を生産しているスパデル社のデュボア社長から招待を受け、生産現場を視察する機会を得ました。正確に申し上げると、スパデル社は統括会社で、ベルギーの2か所の他、フランス、英国でもミネラルウォーターの生産をしており、「スパ」の町にある工場は「スパ・モノポール」という名前の子会社です。スパ・モノポール社は13000haの広大な敷地(高原地帯)に42の水源を有し、地下20~200mを流れる自然水を無処理でボトル詰めしているとのことです。町の中心部に位置する工場は完全に自動化された設備を有しており、1時間に4万本のペースでボトル詰めの作業が行われている風景は圧巻でした。デュボア社長によればスパの町でミネラルウォーターが採取され、海外に輸出されるようになったのは1583年だそうですが、現在のスパ・モノポール社が設立されたのは今から100年ほど前の1912年であり、その後、1920年代にこの会社をデュボア社長の祖父が取得し、以来、この会社はデュボア一族が経営しているとのことでした。スパの地下水はミネラル成分や塩分が少なく飲みやすい(乳幼児向き?)のが特徴であり、また炭酸の量も少ないので炭酸水の場合は炭酸を加えているようです。スパデル社の年間売上額は210百万ユーロ(約300億円)で、ミネラルウォーターの販売会社としてはヨーロッパでは14~15番目の中堅企業です。日本への輸出は1990年代に具体的な取引話があったものの、未だ実現していないとのことでした。
<ゲント市で開かれる花の祭典>
 ベルギー第3の都市であるゲント市が、5年に1度、「フローラリー」という花の祭典を開催していることを御存じでしょうか。何と、ベルギー独立前の1809年に初めて開催され、これまで200年以上も続いているというから驚きです。前回の開催が2010年ですから次回は2015年ということになるのですが、企画の大幅な変更が予定されるために実際には2016年の開催になるようです。毎回4~5月にゲント市内のいくつかの会場を舞台に10日間に亘って開催され、次回も延べ30万人近い入場者を見込んでいるとのことです。会場の総面積は45000㎡あり、屋内庭園としては世界最大の広さです。私は、3ヵ月ほど前に、このイベントを主催する民間団体のヴェルメルケ理事長と知り合っていたのですが、先週、ブリエルス・東フランドル州知事が知事公邸で主催してくれた昼食会で再会し、2016年の次回祭典に日本が特別招待国として参加する可能性について意見交換しました。この食事会にはテルモント・ゲント市長やピエット・ステイール日本名誉総領事らも同席してくれました。2016年は日本・ベルギー外交関係樹立150周年の年ですので、日本が特別招待国としてこの一大イベントに参加出来ればすばらしいことですね。 ベルギー第3の都市であるゲント市が、5年に1度、「フローラリー」という花の祭典を開催していることを御存じでしょうか。何と、ベルギー独立前の1809年に初めて開催され、これまで200年以上も続いているというから驚きです。前回の開催が2010年ですから次回は2015年ということになるのですが、企画の大幅な変更が予定されるために実際には2016年の開催になるようです。毎回4~5月にゲント市内のいくつかの会場を舞台に10日間に亘って開催され、次回も延べ30万人近い入場者を見込んでいるとのことです。会場の総面積は45000㎡あり、屋内庭園としては世界最大の広さです。私は、3ヵ月ほど前に、このイベントを主催する民間団体のヴェルメルケ理事長と知り合っていたのですが、先週、ブリエルス・東フランドル州知事が知事公邸で主催してくれた昼食会で再会し、2016年の次回祭典に日本が特別招待国として参加する可能性について意見交換しました。この食事会にはテルモント・ゲント市長やピエット・ステイール日本名誉総領事らも同席してくれました。2016年は日本・ベルギー外交関係樹立150周年の年ですので、日本が特別招待国としてこの一大イベントに参加出来ればすばらしいことですね。
<シント・ニクラースの版画展>
  先月末、シント・ニクラース市(ブリュッセルの北西47km:人口72300人)の展示会場で日・ベルギー合同版画展が開催されました。出展したアーティストは日本人が28人、ベルギー人が20人で、150以上の作品が広い会場を埋め尽くしました。私は初日に行われたオープニング式典(350人が出席)に招待され、アーティストの皆様からそれぞれの作品について直接説明を受けることが出来ました。この版画展のユニークさは、日本・ベルギー双方のアーティストの作品を順不同に並べていることで、一見する限り、どれが日本人の作品で、どれがベルギー人の作品なのかが不分明です。日本人の作品の中には浮世絵をモチーフにしたものや金魚をデザインしたものがあって、作者の国籍がすぐわかるものもありますが、大半は抽象的な作品ですので、判りにくいのです。しかし、不思議なことに、会場を2周すると両国のアーティストの感性の違いのようなものが何となく判り始め、作者の国籍を推量することが容易になります。一口に「版画」と言っても様々な製作技法があり、絵や写真と見紛うものもあります。この合同版画展は3年前に京都で開催して成功をおさめ、その時の出展者の何人かが有志となって今回のシント・ニクラース市での展覧会になったとのことでした。私は、開会の挨拶の中で、2016年の日・ベルギー外交関係樹立150周年のお祝いの年に第3回目の合同展を開催してくれるようにお願いしました。 先月末、シント・ニクラース市(ブリュッセルの北西47km:人口72300人)の展示会場で日・ベルギー合同版画展が開催されました。出展したアーティストは日本人が28人、ベルギー人が20人で、150以上の作品が広い会場を埋め尽くしました。私は初日に行われたオープニング式典(350人が出席)に招待され、アーティストの皆様からそれぞれの作品について直接説明を受けることが出来ました。この版画展のユニークさは、日本・ベルギー双方のアーティストの作品を順不同に並べていることで、一見する限り、どれが日本人の作品で、どれがベルギー人の作品なのかが不分明です。日本人の作品の中には浮世絵をモチーフにしたものや金魚をデザインしたものがあって、作者の国籍がすぐわかるものもありますが、大半は抽象的な作品ですので、判りにくいのです。しかし、不思議なことに、会場を2周すると両国のアーティストの感性の違いのようなものが何となく判り始め、作者の国籍を推量することが容易になります。一口に「版画」と言っても様々な製作技法があり、絵や写真と見紛うものもあります。この合同版画展は3年前に京都で開催して成功をおさめ、その時の出展者の何人かが有志となって今回のシント・ニクラース市での展覧会になったとのことでした。私は、開会の挨拶の中で、2016年の日・ベルギー外交関係樹立150周年のお祝いの年に第3回目の合同展を開催してくれるようにお願いしました。
<モレチュス家の古城>
  前回の「よもやま話」でアントワープのプランタン・モレチュス博物館(ユネスコの世界文化遺産)を訪問したことを御紹介しましたが、その折に、モレチュス家の邸宅に招待され、昼食を御馳走になりました。この邸宅はアントワープから南東に10kmほど離れたボーコウトという小さな町にあり、17世紀に建てられたという古城でした。車で現地に到着した私ども夫婦が正門を過ぎてから道に迷うほど広大な敷地で、城内には大小のサロンがいくつもあり、そのうちの1つは中国の古美術品で飾られておりました。昼食には御子息や令嬢らの御家族も夫妻で参加され、楽しい食事会になりました。ご主人のレイナルド・モレチュス氏は実業家で、現在はベルギー貴族会の名誉会長を務めておられますが、先祖の家業であった印刷業は何代も前の19世紀後半には300年の歴史を閉じ、廃業しているとのことでした。御夫人はリンブルグ・スティルム伯爵家の御出身で、子供の頃は自宅で家庭教師から教育を受け、学校に通ったことがなく、今でも数を数えるのが苦手であるとのお話には驚きました。私は、この「よもやま話」シリーズで「古城に住むベルギー貴族」を何人も紹介してきましたが、モレチュス家はそうしたベルギー貴族の代表格ですね・・・。 前回の「よもやま話」でアントワープのプランタン・モレチュス博物館(ユネスコの世界文化遺産)を訪問したことを御紹介しましたが、その折に、モレチュス家の邸宅に招待され、昼食を御馳走になりました。この邸宅はアントワープから南東に10kmほど離れたボーコウトという小さな町にあり、17世紀に建てられたという古城でした。車で現地に到着した私ども夫婦が正門を過ぎてから道に迷うほど広大な敷地で、城内には大小のサロンがいくつもあり、そのうちの1つは中国の古美術品で飾られておりました。昼食には御子息や令嬢らの御家族も夫妻で参加され、楽しい食事会になりました。ご主人のレイナルド・モレチュス氏は実業家で、現在はベルギー貴族会の名誉会長を務めておられますが、先祖の家業であった印刷業は何代も前の19世紀後半には300年の歴史を閉じ、廃業しているとのことでした。御夫人はリンブルグ・スティルム伯爵家の御出身で、子供の頃は自宅で家庭教師から教育を受け、学校に通ったことがなく、今でも数を数えるのが苦手であるとのお話には驚きました。私は、この「よもやま話」シリーズで「古城に住むベルギー貴族」を何人も紹介してきましたが、モレチュス家はそうしたベルギー貴族の代表格ですね・・・。
| 