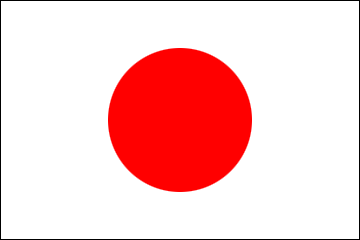Chizuの部屋
第2回 補佐官のお仕事NATO事務総長特別代表 皆さん、こんにちは。 今回もこうして近況などをお伝えできることを、とても嬉しく思っています。 1月20日には、岸田外務大臣がNATOを訪問され、その際に本物の”Chizuの部屋”にもお寄り頂きました。激励のお言葉も頂き、とても光栄でした。また、私が補佐するスクールマン特別代表にもお引き合わせ出来て、とても良い機会でした。この際の3ショットの写真には首から下げた鍵が写っていますが、実はこれは”Chizuの部屋”の鍵で、いつも首から下げています。アジア系が少なく不思議な顔で通り過ぎる人が多いNATOにおいて、これは「部屋があるんだよ」という誇りを無言で示す、まさしく重要な鍵なのです。 さて今回は、「NATO事務総長特別代表(女性、平和、安全保障担当)補佐官」の仲間たちとそのお仕事についてご紹介します。 スクールマン特別代表は、オランダ出身の外交官。在マケドニア大使を経て、2014年10月に着任しました。月に数回の出張と頻繁な要人来訪に対応する目まぐるしい毎日を、鮮やかにこなしています。やるべきことは厳しく要求する面と、3人の母親らしい温かい面を合わせ持つ、懐の深い人物です。この特別代表のポストは2010年に新設され、初代はノルウェー出身のマリ・スカレ氏が務めました(ノルウェーからの自主派遣)。スカレ氏は、2014年9月に東京で開催された「WAW!(女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム)」にも招へいされ、安倍総理や江渡防衛大臣(当時)にも表敬訪問しています。その後、この特別代表はNATOの恒久的ポストへと格上げされ、これと同時に現職のスクールマン氏が着任しました。 特別代表を支えるスタッフは現在3人。補佐官Lさん(オランダ出身)と、インターンSさん(ブルガリア出身)、そして私です。Lさんはアフガニスタンでの経験と幅広い人脈を背景に、恐ろしい勢いで仕事をしています。それは、昼休みにNATO内のジムで運動中であってもブラックベリーからメール返信をするほどの凄まじさです。その綿密さとバイタリティーは計り知れません。またSさんは、溌剌として太陽のような性格で、とても社交的です。いつもすれ違う多くの人に話しかけます。彼女のオフィスに居ると様々な人が頻繁に挨拶にやって来るのに驚きます。5か国語話せるSさんはとてもチャーミングで、たまに男性陣がチョコなどをプレゼントに来るのですが、「いらない!」ときっぱり断る彼女を見ていると、「ステキ女子かくあるべし」と参考になります。私の場合、見習ったことを発揮する場面もないのですが。 ところで、女性やジェンダー関連の職務というと、女性職員ばかりというイメージがありますよね。でも、NATOでは男性職員もこれらの職務に携わっています。例えば、我がチームのカウンターパートである国際軍事局(IMS:International Military Staff)のジェンダーアドバイザーは男性(スペイン陸軍中佐)ですし、NATOのオペレーションを司る欧州連合軍最高司令部(SHAPE:Supreme Headquarters Allied Powers Europe)のジェンダーアドバイザー補佐官2名も男性(ドイツ陸軍中佐、フランス陸軍中佐)です。面白いのは、彼らは特段ジェンダーに関する経験や知識が買われたわけではなく、ある日突然指名されて着任した、というような背景を持っていることです。一応周囲に聞いてみましたのであえて補足すると、これはイレギュラーな人事(仕事のパフォーマンスが悪いので男性にとっては馴染みの薄いジェンダー関連ポストに配置するといったような悪い意味の人事)などではないとのこと。彼らはごく自然にそのポストに就いて、ジェンダーに関する課題に熱意をもって当たっています。もちろん最初は戸惑ったけど、と付け加えつつ。NATOではそれだけ、ジェンダーに関する認識が浸透しているということを感じますし、女性職員の側も「女性vs男性」といったような対立構図に陥ることなく、ごく自然に男性と女性が協力している、という印象を受けています。 続いて、補佐官の仕事について紹介します。 補佐官の仕事は、特別代表を支えることです。では特別代表の地位はというと、「女性、平和、安全保障」に関してNATO事務総長から責任権限を委任されNATOを代表する存在、ということになります。じゃあ、「女性、平和、安全保障」とは? この説明の前に、いま国際社会で問題認識が高まっている「紛争下の性的暴力」についてお話したいと思います。皆さんは、この言葉にどんなイメージを持たれるでしょうか。日本では、「紛争下」といえば基本的には海外で起こっていること、という認識でしょうから、あまり身近ではないかもしれませんね。こうしてNATOに派遣されている私も、数年前まで「紛争下の性的暴力」について、しっかり考えたことはありませんでした。 少しNATOから話はそれますが、私がこの問題について知った、東ティモールPKOでの経験について紹介したいと思います。国連では、全PKO要員に対する「ジェンダー教育」を義務付けており、私も派遣前及び派遣直後の導入教育でこれらの教育を受け、紛争影響国では特に女性が危険にさらされるということを知識として知りました。そして、軍事連絡要員として実際に派遣された際、東ティモールの村落等での情報収集活動を通じて様々な経験をしました。性的暴力の被害者である未婚の母に出会ったこともありました。6人いる子どもの父親は全て別人と聞き、彼女の過酷な人生を思うと今も胸が締め付けられます。仕事仲間の青年から複雑な出自を告白されたこともありました。彼の母親は、紛争時に生存のためやむを得ず敵軍人に身を売った結果彼を産み、その後苦しみ抜いて若くして亡くなったそうです。 この経験は、紛争下の女性の保護や平和構築への参画を促すため女性PKO要員の増加が求められているという、国際的なニーズを体感する機会になりました。一般的に言って女性の軍事要員がいた方が現地女性との接触も増えますし、現地女性を参画へと力づける活動も容易になります。そこで国連は、PKO参加国に対して、その国の軍等における女性比率と同等の女性PKO要員の参加を要請しています。例えば、日本であれば自衛隊における女性比率は6%弱なので、PKO派遣部隊でもその6%弱が女性であることが望ましいということです。この基準を達成する国はまだ少ないようですが…。 しかし、果たして「紛争下」では性的暴力はつきもので、古今東西、これは仕方のないことなのでしょうか。「戦争なんだから。レイプなんて当たり前だろう」という見解があっても不思議ではないのかもしれません。 「東コンゴでは、兵士でいるよりも女性でいることのほうが危険である。」これは元MONUC(国連コンゴ民主共和国ミッション)東部司令官であったパトリック・カマート退役少将の有名な発言です。コンゴは、PKOが展開していてもなお紛争手段として女性への性的暴力が続く地域だそうです 。「戦術としてのレイプ」に対して国際社会の問題認識が高まったのは、旧ユーゴスラビア、ルワンダ、コンゴ、リベリア等で大規模で凄惨なレイプが行われたこと等からです。ルワンダで起こった「民族浄化」について聞いたことがあるでしょうか。ツチ族の女性の多くがレイプされ、殺されました。また多くの女性がレイプの結果出産を余儀なくされました。これは、レイプがジェノサイド(大量虐殺)を遂行する手段として使用された有名な例です。またコンゴでは、25~50万人の女性がレイプされたといわれています。レイプされた女性たち(時には男性が対象となる場合もあります)はどうなるのでしょう。 レイプは、時として敵勢力の攻撃の報復、また時として民族浄化、ある時は恥や傷また病気によって敵の士気を下げるために行われます。レイプの結果トラウマやぞっとさせるような傷を持つ男女が側にいることで、家族や村全体が上手く運営できなくなってしまう、と言われています。身内の女性や少女たちが敵にレイプされたら、そのコミュニティの男性たちはどう感じるのでしょう。多くの例ではそうした女性たちは夫たちから離縁されていて、必然的にコミュニティから排除され、甚だしい精神的苦痛と貧困に苦しむ余生を与儀なくされます。離縁した夫たちもコミュニティから後ろ指を刺されながら暮らし続ける例があるそうです。この例のように、レイプは、男女双方に対してその影響が大きいからこそ、敵勢力の戦力低下のために組織的に行われてきました。 とにかく国際社会は、特に1990年代頃から、身の毛がよだつような「戦術としてのレイプ」を目の当たりにしてきました。そして、これが2000年の国連安保理決議1325号「女性、平和、安全保障」決議へとつながりました。 NATOは、このような国際社会の問題認識を踏まえつつ、NATO自体のオペレーション(アフガニスタンやコソボ等)を通じて、ジェンダーの視点を政策や作戦に取り入れることが作戦地域の安定化や現地女性等の安全保障に資することを、経験として学んでいます。そしてこれらの経験を蓄積し、必要な政策がNATOのあらゆる作戦や活動に反映されるよう1325号履行に係る「行動計画」を作成して各種施策を推進するとともに、国連を始めとした関係国や機関等と連携を図り、軍事機関としてはおそらく最も進んだ取組みを行っています。国連決議1325号やNATOの具体的取組みについては、改めて詳しく紹介していきたいと思います。 私は、このような問題認識と目まぐるしい日々の中、毎日忙しい特別代表を支えるべく補佐官として業務に当たっています。1日も早く、NATO職員としてしっかりとNATO特別代表を支える業務ができるよう努力していきます。もちろん日本は、「戦術としてのレイプ」も、紛争下の性的暴力も許さない国なのです。女性として生まれたことで自動的に生存の危機や苦痛を強いられるような、そんな社会は無いほうがよいでしょうし、日本はそういった社会を無くすための取組みを行っているアジアの国なのだと胸を張って、明日からもNATOで勤務していきます。 それにしても、NATOの人たちはなんともスタイリッシュな服装で勤務しています。こんなことなら、ハイヒールを持ってくるのでした…。 1 内閣府男女共同参画局「共同参画」2012年3月号、「PKOにおける文民の保護とジェンダー(2)」より引用   |