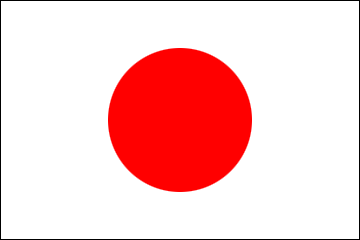Chizuの部屋
第3回 軍事作戦にジェンダーの視点をNATO事務総長特別代表 皆さん、今回もご来訪くださりありがとうございます。 先月のことになりますが、3月8日は何の日かご存じでしょうか。正解をズバリ当てられた方は素晴らしいと思います。かくいう私も、恥ずかしながら数年前までは全く知りませんでした。 この日は「国際女性の日(International Women’s Day)」です。欧州では、この日を祝ってご馳走を食べたり、「女性の日おめでとう」と挨拶したりするところもあるそうです。インターネットで少し検索してみるだけで、多くのイベントが主に海外で開催されていることに気づかれるはずです。 私の上司であるNATO事務総長特別代表(女性、平和、安全保障担当)も、その日に開催されたハーグ(オランダ)やブリュッセルでの関連会合に参加し、「ジェンダー」や「女性、平和、安全保障」に関するNATOの取組み等について力強く発信しました。今年の共通フレーズは、「実現させよう(Make it happen)」でした。「ジェンダー」という言葉は非常に幅が広いので、ときに捉えどころのない大海原のように感じてしまいます。「女性、平和、安全保障」という主題も、一見すると平和な国々では縁遠いように思われます。特別代表は、このような主題について「アフガニスタンやコソボだけの問題としてではなく、身近な問題として考えてみよう」というメッセージで語りかけました。 さて、今回は、スウェーデン軍のジェンダー課程についてご紹介します。 先般、私はスウェーデン軍国際センターで実施された2週間のジェンダー課程教育に参加しました。これは、作戦部隊指揮官等を直接補佐するジェンダー・フィールド・アドバイザー等を養成する課程であり、主として平和作戦においてジェンダー関連業務に従事する要員、特に軍の要員を対象としたものです。軍の実施するジェンダー教育の中では間違いなく世界最先端のものであり、毎回定員に対し数倍の受講希望者が応募するそうです。私は、数年来この課程への参加を熱望していたのですが、私の派遣元である防衛省陸上幕僚監部防衛部の強力なバックアップのおかげをもって、幸いにも今回参加することができました。当課程への自衛官の参加は初めてであったため、受け入れ側からも温かく迎えて頂きました。 学生は総勢26名。「ジェンダー」というだけあって、やはり学生の大半が女性と思われますか?いえいえ、学生の4割以上にあたる11名が男性でした。ジェンダー・フィールド・アドバイザーには、男性も就くのです。クラスは軍人と文民混交であり、出身国も幅広く、欧州諸国のほか、アフリカからも3人が参加。アジアからは日本人の私1人のみでした。 なお、この課程のために施設を提供し、その教育の大半を担任しているのはスウェーデン軍ですが、北欧5か国協力の一環として、教官陣にはノルウェー、フィンランド等の軍人もいます。また、NATOもこの課程のスポンサーとなっています。スウェーデンはNATO加盟国ではないものの、ジェンダー分野での先進性が認められ、NATOの教育の一部として認定されているというわけです。一つのプロジェクトを複数の国で協力して実施し、成果も共有するというのはいかにも欧州らしいやり方ですね。 ともかく、この課程はNATOに公式に認定されたものとして、NATOのジェンダー政策やNATOによる作戦に基づいた内容でした。また、学生の中には、アフガニスタンにおけるNATOの「確固たる支援任務」(RSM: Resolute Support Mission)のジェンダー・フィールド・アドバイザー等として勤務予定の者も含まれており、教室にただならぬ緊迫感が漂うこともありました。 教育は、「ジェンダー」の基礎知識に関する講義から始まります。「ジェンダー」の概念、国連安保理決議1325号「女性、平和、安全保障」及び関連決議の経緯と意義、NATOの作戦レベルにおける「ジェンダー視点」の反映に関する指針など。 そして、教育内容は次第に深くなっていきます。教育4日目には、あるドキュメンタリー映画を見て、性的暴力への問題認識を深めました。映像を視聴する前に、「心理戦」に詳しい将校が注意事項を述べます。「映像を見て強烈な刺激を受け、心身に何らかの反応が出ると思うが、それは自然なこと。見終わった後に、感想を言いたければ近くの人に話せばいいし、はっきり伝えられなかったら自分に起こった身体的・精神的変化について伝えてもいいし、言いたくなければ何も言わなくてもいい」。こうした教育手法にも、逐一感心してしまいます。 この映画は、紛争の影響を受けたコンゴ民主共和国における、性的暴力の実像を浮き彫りにしたものでした。まず、レイプ被害者の女性たちが登場します。レイプは、時に集団でかつ残忍に行われ、被害者は身体に深い傷を受けます。緊急手術が必要な場合や、歩行や排尿も困難になる場合もあり、何カ月も起き上がれない、さらにコミュニティからは排除されて行き場もない、そのような痛ましい姿が描かれます。そしてレイプ被害者を支援する現地女性警官の活動とそのジレンマ。レイプ被害者は後を絶たず、加害者は罰せられることもなくまたレイプを続けるという現実。レイプ加害者(レイピスト)へのインタビューも登場します。私服で銃を担ぎ、顔を隠した男たち。「今までレイプした数?数えきれないさ。」、「女房とずっと離れてるんだぜ。何が悪いっていうんだ?」、というレイピストのコメントが容赦なく映し出されます。紛争下の性的暴力は、「戦争の兵器(Weapons of War)」とも呼ばれ、レイプは時に、武装勢力内における帰属意識の確認や団結の強化にも利用されます。つまり、「俺たちの仲間だったら、お前も(敵対勢力の)住民をレイプして来い」、「1人の女性を全員でレイプすれば、仲間の絆が増す」ということです。 映画の後、私は口の渇きと動悸を感じました。同種の映像を見た経験はありましたが、この重いテーマに接する時には、必ず胸が苦しくなります。クラスメートには映画の舞台となったコンゴ民主共和国の女性軍人もおり、彼女も交えて皆で意見を交換しました。 その後小グループに分かれ、討議の時間がありました。そのシナリオはこうです。 「貴官は、コンゴ民主共和国で活動中のPKO部隊の中隊長である。パトロール中に、レイプされたと思われる13歳の少女が森の中から出現した。彼女の話によると、武装勢力に他の少女2人が誘拐されている模様。その他の情報に基づき、武装勢力の所在地や加害者を特定できる状況である。なお当該PKOでは、『文民の保護』がマンデート(任務)に規定されている。中隊長としての貴官の判断は如何。」 私の参加した小グループでは、各人の意見は面白いほどバラバラでした。鍛えられた太い腕に「人生は常に戦い」とのタトゥーが刻まれたある国の海兵隊員は、こう言います。「俺たちは『文民の保護』ができるんだから、今すぐ少女奪回作戦を敢行すべきだ。」アフリカ出身の文民女性は、「正気なの?まずやるべきは、武装勢力の親分にコンタクトして、少女を返すように交渉することでしょ。」と主張します。 当グループの議論の結論を紹介すると、ここで判断すべき事項は3点、すなわち(1)直面するレイプ被害者である少女の保護、(2)誘拐された少女の保護、(3)今後の対応(予防)。ここで忘れてはならないのは、我々(シナリオの主体)は軍の要員であるということで、その行動は軍に適したことに限定されるべきなのです。例えば(1)については、保護した少女を軍がコミュニティにそのまま届けるのが果たしてよいのか、また捜査のためとはいいつつ、軍人が被害状況等について調査をするのが本当に適切なのか等については、考える余地があるでしょう。文民女性からは、軍のジープや軍服を着た軍人が少女をコミュニティに送れば人目につき、彼女がレイプされた事実が周知の事実となるのでは、という意見もありました。なるほど、参考になります。軍がレイプというセンシティブな事象に対応するためには、国際機関やNGO等の文民組織と連携するのがより良い対応ということでしょう。また、(2)の誘拐された少女の保護の要領について、選択肢はいくつかあるでしょうし、(3)の今後の対応については、被害現場周辺の脆弱性(レイプ被害を生みやすい環境)等を調査し、軍によるパトロールの強化や、少女の登下校時のエスコートなどがありうるかもしれません。これは軍にしかできない役割です。 こうした討議を通じて、「被害者の保護」や「ジェンダー」に関して考慮すべき事項について思いを馳せ、「ジェンダー」に関する軍の役割は何か、作戦における「ジェンダーの視点」とは何か、ということを少しずつ理解していく仕組みです。 そして、次のステップは、軍事作戦にジェンダーの視点を反映させる要領について具体的に学ぶ段階です。軍人対象の教育だけあって、軍組織の意思決定手順に関する基礎知識が必要とされます。 ここからは、若干専門性が強い話になってしまいますが、努めて簡単に概要を紹介します。作戦部隊指揮官を直接補佐するジェンダー・フィールド・アドバイザー等の役割は、当該部隊の実施する作戦及び業務の全てに、ジェンダーの視点を反映させることです。ということは、当該部隊が担う、人事・服務・情報・作戦・兵站・計画・通信・教育訓練・民軍連携等の全分野において、ジェンダーについても十分な考慮が払われるように、司令部の各スタッフと連携しつつ、指揮官を補佐しなければなりません。そこで、架空の軍事作戦のシナリオに基づいて、「状況の特質」、「作戦見積」、「全般作戦計画」、「行動命令」等に関する具体的な業務要領を学びます。意思決定手順の観点でも、NATO基準に基づいた本格的な教育と言えます。 「軍事作戦へのジェンダーの視点の反映」は、日本にとっては新鮮なテーマですので、NATO等から学んだ内容を、今後多くの方にご紹介していきたいと考えています。ただし、専門性が強くなりますので、本コーナーではなく、別の機会になるかもしれません。 ちなみに、この教育において最も印象的だったのは、「抵抗者への対応」という課目でした。「ジェンダー」に無関心、または反発する人々に対して、ジェンダー・フィールド・アドバイザーとしていかに対応するかという課目です。討議の後、それぞれのグループで考えた対応策を寸劇で紹介しました。無関心層の関心を惹く工夫や、「ジェンダー?それは女こどもの話で自分には関係ない」と聞く耳をもたない指揮官への説明要領、仲間の増やし方などで、完全なる解決策とはいかないまでも、各グループの寸劇はどれも印象的なものでした。 ところで、北欧といえば、ジェンダー先進国というイメージがありますが、どうも大昔からそうではなかったようです。面白いのは、例えばノルウェーとスウェーデンの間にも差異があることです。労働者全体に占める女性の割合が40%というノルウェーでは、「ユニセックス文化」が浸透しています。ノルウェー軍では、今年、イスラエルに次いで世界2例目となる女性の徴兵制度を開始しました。同軍では、全ての職域で既に女性に門戸を開いています。最近では、潜水艦の女性艦長(大佐)や、PKO史上初の女性司令官(少将)も輩出しています。この背景には、男女の生活区画の区分をなくした(または限定した)ということがあるようです。兵士のシャワーもトイレも男女共用(もちろん個室ですが)、居室すら男女混在ということだそうです。ノルウェー軍人は、「自分たちには、男女という性別は関係なく、軍人同士として尊敬しあう文化がある」と胸を張ります。世論についても、「女性も一国民として、国防を担う徴兵に参加するのは義務であり自然」との意見が多いそうです。これに対して、スウェーデンでは、慣習上「男女別」が当たり前であるため、ノルウェー的な「ユニセックス」には抵抗があり、軍内でも全般的にノルウェーよりは保守的要素が強いとのこと。「ジェンダー」とは社会的に創られたもの。要は人間が、その土地や時代等によって形作ったものです。軍は社会の縮図であり、軍における「ジェンダー」も、各国様々なようで興味深い限りです。 最近、カウンターパートの1人から、とても印象深い、人生を変えるような言葉を聞きました。 彼女は、NATOの作戦を司る欧州連合軍最高司令部(SHAPE:Supreme Headquarters Allied Powers Europe)のジェンダー・アドバイザー。とても物腰の柔らかい穏やかな女性です。NATO非加盟国のスウェーデン出身(予備役将校)ながら、司令部においてNATO作戦の全てに関わりジェンダー視点を反映させる要職に就いています。いわく、「今やスウェーデンはジェンダー先進国と言われているし、自分はまるでジェンダー分野の成功者のように評されているが、これまで自分は、散々泣いてきたし、叫んできたし、頭をかかえて悩んだし、うめいてもきた。家族には、もうやめれば、と何度となく言われた。でも自分は開かないはずのドアを10枚も開けてきたと思う。」と。そして「今度、これまでの経験を全部教えてあげるわ。こっそりね。」と肩を寄せてくれました。 NATOには強くて美しい人がいます。それがNATO非加盟国の人であっても。 「女性、平和、安全保障」は、世界的に今後ますます進化していく分野といって間違いありません。そして、この分野で日本とNATOがともに取り組むことは、日NATO協力の進展のみならず、国際的な安全保障環境の安定化への寄与につながると考えています。今後も、NATOでの個人の経験をこうして皆さんと共有しつつ、自分のできることを探して、「Make it happen」を目指していきます。 次回は、ジェンダーとネットワークについてお伝えしたいと思います。 

|