Chizuの部屋
第5回「NATOジェンダーウィーク(その1)」NATO事務総長特別代表 皆さん、こんにちは。 NATO本部の実際のChizuの部屋、どんどん物が増えて充実してきました。とうとうキャスター付きの小さな棚を持ち込み、エスプレッソのみならず、煎茶、抹茶、玄米茶に梅こぶ茶まで品ぞろえしたのを見て、同僚は「まるで和製スーパーマーケットだね」と冗談を言っています。部屋への来客も増えているので、そのうち「お品書き」でも作ろうかと考えています。 今回は、まずベルギー軍のお話から。 7月21日はベルギー王国独立記念日で、軍隊、警察、消防、救急等によるパレードが王宮周辺で開催されました。パレードに先立って登場されたフィリップ国王は、4つ星の軍服姿。軍用車に立たれ、沿道を見守る国民(観衆)の前を、騎馬部隊の護衛を受けながら進まれました。ブリュッセルに古くからある道、特に王宮周辺の道路はそれほど幅広ではありません。「王」そして「王国」の軍隊は、国民の前をほんの間近に行進して行きました。また、騎馬部隊通過後の合間をぬって、道路のあちこちに散在するボロ(馬の落とし物)を清掃車がテキパキと片づける様子に沿道の人々が拍手したり、パレードに軍用犬が参加しているのを子供たちが珍しがったり。こんな一幕も含め、沿道からは終始温かな視線が注がれていました。私は観衆の一人として王宮裏の沿道からの見学でしたので、観閲台からの眺めとはまた異なる軍の姿を垣間見られたのかもしれません。 パレードといえば、「女性自衛官部隊指揮官」として参加した2010年の自衛隊観閲式を思い出します。約280名の陸海空女性自衛官は、スカートを着用し、旗手を除き全員がハンドバッグ携行で行進しました。陸自女性自衛官部隊が、迷彩服姿に64式小銃携行で行進した年も過去にはあったようですが、遠目にも確実に女性ばかりとわかるこの臨時編成の部隊、もはや自衛隊観閲式の恒例になっていると言えそうです。 ベルギー軍に話を戻します。現在の職務にある以上、今回のような機会には、やはり女性の存在が気になってしまいます。ベルギー軍のパレードでは、どんな部隊に、どんな服装の、どれほどの数の女性がいるのか。そして、彼女たちはどんな風なのだろう、と。 こうした視点で探すと容易に目で追えるものですね。騎馬部隊:全般的に少数ながら指揮官も存在、歩兵部隊:ゼロ、特殊部隊:ゼロ、PKO部隊:ゼロ、士官候補生部隊:一部存在(女性のみキュロットにヒール付ブーツ)、海軍部隊:男女ほぼ半々、空軍部隊:男女ほぼ半々…。旗手その他を除き、部隊の一部を構成する女性たちは、小銃等の武器を携行していました。 各部隊を眺めながら、思いつく限り考えてみました。自分はなぜ女性を探してしまうのか。
また、部隊内にちらほら見られた指揮官の女性を見た時どう感じるのかも、幅広く考えてみました。
私は陸上自衛官ですし、部隊の指揮官も経験したので、どちらかというとジェンダー統合の進んでいる軍には親近感を持てるものと自認しています。ましてや、NATOでジェンダー関連の職務にあるのですから。…それでも今回のベルギー軍のパレードを見るにつけ、肯定的な印象から不思議な感覚までが、大なり小なり自分の中にあることに気づき、「軍の女性」について思いを馳せる機会になりました。国内にいた時より思考の幅が広がるというのは、きっと海外勤務の特権ということでしょう。ちなみに、ベルギー軍は1975年の女性受入から今年で40周年を迎え、軍の女性比率は約7.6%だそうです。 さて、今回のテーマ、「NATOジェンダーウィーク」についてご紹介します。6月、NATO本部で年1回のジェンダーに関する大きな会合が開催されました。同じ週に複数の会合が開催されたため、今年は「ジェンダーウィーク」と呼ばれ、各国から専門家が集まりました。開催されたのは、(1)「国連安保理決議1325号リロード(再装てん)」、(2)「NATOジェンダー視点委員会年次会合」等です。(2)は、NATO加盟国及びパートナー国等から各国代表が参加した会合で、日本からは、外務省から松川総合外交政策局女性参画推進室長が日本代表団長として、また防衛省から陸海空自衛官各1名の合計4名が参加しました。これは、4日間にわたるボリュームのあるものでしたので、次回ご紹介します。 今回は(1)の会合について触れますが、最初に筆者の最もお伝えしたい主題を述べてしまいたいと思います。 それは、NATOにとって、「女性・平和・安全保障」とは、NATOの集団防衛に影響する安全保障上の課題へのアプローチであり、「対テロ」や「サイバー防衛」等と同様に喫緊に取り組むべきものと認識されているということです。 なぜ、このように言い切ることができるのでしょうか。まず、会合の背景から説明していきます。 この会合は、NATOが近年重視して取り組んでいる「安全保障のための科学プログラム(Science for Peace and Security Programme: SPSプログラム)」のうち、「女性・平和・安全保障」に関連する、あるプロジェクトの総括会合として開催されました。 SPS(エス・ピー・エス)プログラムは、NATOのユニークな政策ツール。安全保障に関する特定の分野に関する科学的研究や意見交換等を通じ、NATOとパートナー国等の協力や対話を促進しようとするものです。このシステムのもと、NATO加盟国と関係国の各1か国がペアを組み、共同プロジェクトを行います。この実行組織は民でも官でもOK、という柔軟な一面もあり、各プロジェクトに必要な資金はNATOが負担する仕組み。ちなみに、これまでには、ヨルダンにおけるサイバーセキュリティや、ウクライナにおけるCBRN(化学・生物・放射性物質・核)及びエネルギーセキュリティに関するプロジェクト等、数多くの実績があります。このSPSプログラムは、研究成果に加え、関係国との関係強化という2つのメリットがあるため、NATO側にとって、いわば「1粒で2度おいしい」ものと言われています。これが、グローバル化や複雑化する安全保障課題に対する「包括的アプローチ」と、関係国との協力による「協調的安全保障」を進めるNATOが、このSPSプロジェクトに近年力を入れている理由でもあります。 ここで注目して頂きたいのは、SPSプログラムで取り扱う分野とその効果について。当然NATOが資金を提供するのですから、最終的にはNATOに寄与する内容でないといけません。その分野とは、
そして、3. の「人間の安全保障」には、「女性・平和・安全保障」の課題が含まれており、例えばこの担当の特別代表が配置されていることからもわかるように、NATOはこの分野を特段に重視していると言えます。つまり、NATOにとって「女性・平和・安全保障」に関する課題は、れっきとした安全保障に影響する一つの要因とみなされている、ということを意味しています。 筆者にとって、「ジェンダー」という言葉の範囲や、この分野のNATOの取り組みがあまりに幅広く見え、毎日が暗中模索だった初期の頃、同僚からこんな言葉を聞きました。「NATOは人道機関ではない」―そうか、なるほど。と膝をたたきました。NATOと他の組織との違いについて、ふに落ちた瞬間でした。 その言外に意味するところは、「NATOは、他の国際機関やNGOのように、人道支援そのものを目的とした機関ではなく、あくまでNATO加盟国の集団防衛のための機関(機構)である。だから、『女性・平和・安全保障』や『軍とジェンダー』といった課題へのNATOとしての取り組みは、政治的・軍事的アプローチにより、安全保障環境の改善に直結する、より現実的なものであるべき」、ということです。例えば、同じ「女性・平和・安全保障」の課題に対しても、人道支援の観点からアプローチを行うNGOと、軍を擁し安全保障の観点からアプローチを行うNATOではその役割や政策等にも違いがあって当然と言えます。また、国際機関として国連とNATOを比較した場合も、組織目的が異なる以上、同じ分野を扱うにしても、その活動範囲や焦点にはやはり違いがみられます。さらに言うと、この分野におけるNATOの取り組みは、NATO本部や各戦略コマンドという戦略的なレベルからNATO主導の作戦レベルまでが考慮されており、内容的にも具体化が進んでいるものとの国際的な評価を得ているようです。 このように、筆者はNATOでの勤務を開始してから、「女性・平和・安全保障」という主題は、「女性~」という名称からのイメージとは裏腹に、「安全保障」に直結した意外と硬い分野であることについて、徐々に認識を深めてきたという訳です。 少し話が広がってしまいましたが、いよいよ会合の中身に入っていきます。今回実施されたのは、スペイン(レイ・ホアン・カルロス大学)と豪州(人権コミッション及び豪州軍)による共同プロジェクトを総括する公開会合でした。研究成果の発表と意見交換の場に、NATO本部勤務者、各国NATO代表部勤務者、NATO及び関係国の軍等関係者、市民社会からの専門家等、約120名が参加。プロジェクト実施担当者からの研究成果の報告とともに、前豪州陸軍本部長(陸軍トップ)モリソン退役中将、初代NATO事務総長特別代表のスカレ氏と現職のスクールマン氏等のスピーチを聞くことができました。 この「1325号リロード」という名のプロジェクト、その趣旨は「2000年の国連安保理決議1325号『女性・平和・安全保障』以降、早15年が経過するものの、この理念の履行はいまだ不十分である。今こそ「再装てん」(見直し・再考)してみよう」というもの。過去15年間のデータに基づき、NATO28か国の軍におけるジェンダーの状況を可視化(数値化して客観的にわかるようにすること)しようとする研究です。1325号決議が各国の軍の政策、募集、作戦等に及ぼした影響を分析した上で、豪州軍の先進的な取り組みを参考にしつつ、今後NATOがとるべき方向性について提言するという、興味深い内容でした。 多くのデータが示されました。軍における女性の割合や、ジェンダー統合に関するもの(換言すると「少数派である女性を、軍内にいかに組み入れ戦力化を図るか」)、また軍内の性的暴行防止に関する数値等です。その数値の一部を紹介します。なお、調査の対象はNATO加盟国28カ国です。
ここでは、公表されたデータを客観的にご紹介するに留めたいと思います。筆者は、「よく調べたな」という印象とともに、関係者の執念のようなものを感じています。これは、欧米ではジェンダー平等追求への意識が強いことの証左でしょうし、逆に言えば、こうして可視化しないことには、男性多数の「軍」という特殊な組織では、ジェンダー平等の達成は難しいことを表すものかもしれません。また、この「執念」を裏打ちするものは「女性・平和・安全保障」関連決議であり、軍や安全保障分野にもっと女性を、そして少数派の女性を軍で当たり前に勤務できるようにすること、さらに男女のジェンダー視点を軍の活動に反映していくこと、それらが世界を変え、より恒久的で安定した安全保障環境の構築に有効である、という理念でもあるのです。 (これらのデータはNATOホームページで公開されています。 なお、本稿においては、ベルギー軍のパレードやNATOでの会合の機会を通じた、個人的感想や客観的データを記述したもので、軍の女性や、女性を受け入れている軍を否定する意図ではないことを追記させて頂きます。 



|
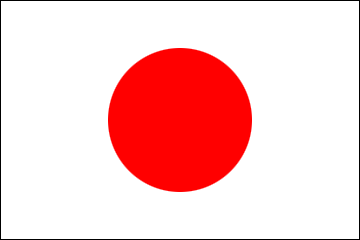


 )
)