第33回 ベルギーで過ごした1年間の大使生活
2013年10月21日
ベルギーに着任して1年が過ぎました。振り返ってみると、随分と短かったような気がします。時間がなさ過ぎて、やりたかったことの半分も出来なかった、というのが正直な感想ですね。私の外交活動の基本は「現場主義」で、デスク・ワークを最小限に抑え、とにかく外に出て友人・知人の輪を広げる、地方を訪問する、企業や教育機関の活動現場を見る、の3点を優先しました。また、情報発信も大使の重要な仕事ですので、大勢の人の前で講演をしたりメディアのインタビューを受ける機会も大切にしました。さまざまなイベントや会食の機会も大いに活用し、ベルギーの政治家や経済界の方々とも大いに知り合うことが出来ました。ベルギー人は総じてオープンな性格で、外国人である私たちとも気軽に付き合っていただけます。また、ベルギーは国土が狭いので地方訪問に飛行機を使うことはなく、車で1時間か1時間半も走れば国中どこにでも行けるのが嬉しいですね。おかげで、この1年間で主要な地方都市はほとんど訪問することが出来ました。各地の教会建築やお城、豊かな自然はベルギーが世界に誇れるものだと思います。食事もおいしい。ポンム・フリット(じやがいものフレンチ・フライ)をつまみながらビールを一杯やるのは多くの日本人にとってベルギー滞在の楽しみの1つなのではないでしょうか。というような訳で私の1年間は瞬く間に過ぎてしまったのですが、さて、2年目の日々をどのように有意義に過ごすか。ウーン、「目下思案中」と申し上げておきましょう。
<注目されるアントワープ市長の動向>
今月の初め、アントワープのバート・デ=ウェーフェル市長が外交団を招いて昼食会を開催しました。私も他用の合間をぬってこれに参加し、市長と短時間ながら言葉を交わす機会を得ました。デ=ウェーフェル市長は、連邦議会の最大勢力である「新フランドル同盟(N-VA)」の党首であり、フランドル地方(オランダ語圏)の一層の自律(分離)と王室の権限縮小を主張し、近年大きく勢力を伸ばしていることから、ベルギーでは「時の人」であり、来年5月の総選挙を前にその動向が注目されています。私から市長に対して過去の訪日経験を伺うと、「未だ一度も日本を訪問したことはない」との返事でした。来年秋にアジアの数か国・都市を訪問する予定があるとのことでしたので、その折には是非日本も訪問するよう申し上げました。デ・ウェーフェル市長はかつては100kg以上も体重がある「巨漢」だったようですが、昨年の選挙を前に大いにダイエットをして大変スマートな政治家に変貌しました。外交団や地元経済界の代表を前にしたスピーチは流暢な英語で行われ、その後の各参加者との懇談も英語で行われました。総じて、フランドル地方の人は政治家に限らず皆さん英語がお上手なのですが、それにしてもデ・ウェーフェル市長の英語力には驚かされました。
<東京で開かれた今年2回目の欧州大使会議>
日本の外交慣例では、毎年1回、東京において地域別の大使会議が開かれることになっているのですが、欧州大使会議については、2月に続いて今年2度目の開催となりました。ただ、日本の会計年度(4月~3月)で言えば、2月の会議は前年度ですので、「各年度に1回」ということに変わりはありません。まあ、開催時期が例年に比べて少し早まったということです。10月15日-17日の2日半に亘る会議では様々なテーマについて外務省の幹部と出先大使との間で発表や質疑応答が行われたのですが、この間、安倍総理及び岸田外務大臣との面会に加え、自民党外交部会や経団連との意見交換も行われました。また、今回は、アベノミックスについて学識経験者から意見を聞く機会が設けられたほか、大使が外国プレスからインタビューを受ける場合を想定したメディア・トレーニングも初めて行われました。極めて充実した大使会議でしたが、この会議期間中、東京は台風の襲来を受け、通勤がとても大変でした。私は久しぶりにギネス記録並みの満員電車に乗車し、東京勤務の厳しさを実感しました。
<2つの日本企業>
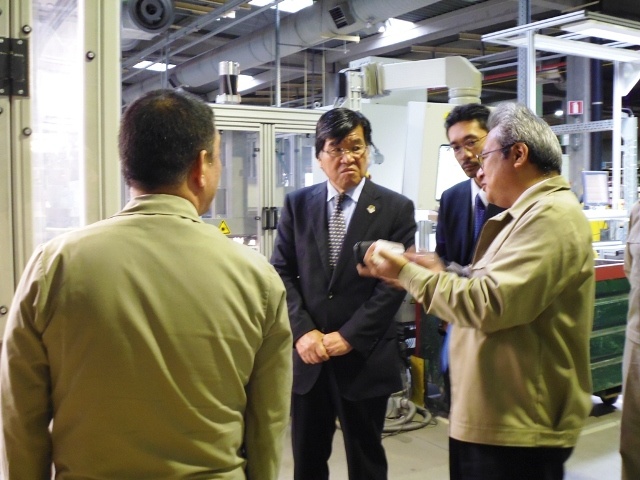 10日ほど前に、サンギラン市(ブリュッセルの南西70km)にあるNGKセラミックス・ヨーロッパ社を訪問しました。この会社は名古屋市に本社がある「日本ガイシ」の子会社で、1985年に設立されています。「日本ガイシ」は海外10ヵ国に17の生産拠点を有しているそうですが、サンギランの工場はその中でも最初に出来た海外生産拠点だそうです。製造しているのは自動車排気ガスを浄化するための「ハニセラム」という触媒担体で、販売先は触媒そのものを製造している企業です。これを次の工程で排気管中央の膨らんだ部分の内部に取り付け、最終的に排気管部品となって自動車製造会社のもとに届くという流れです。セラミック製品である「ハニセラム」の外観は円柱形のトイレット・ペーパーのような形ですが、横断面には蜂の巣のように極く微小な穴が無数に(1万個以上?)空いており、その穴の壁面(厚さは0.05mm)に触媒を塗ると、排気ガスが通過した時に化学反応が起こり、有害なガスが無害化されるという仕組みです。トイレット・ペーバーのサイズの「ハニセラム」の場合、穴の壁面の総面積はサッカー・グラウンド2面分に及ぶそうですから驚きです。正規の従業員は日本人7名を含めると263人で、ベルギーは労働コストが高いので機械化がかなり進んでいるとのことでした。 10日ほど前に、サンギラン市(ブリュッセルの南西70km)にあるNGKセラミックス・ヨーロッパ社を訪問しました。この会社は名古屋市に本社がある「日本ガイシ」の子会社で、1985年に設立されています。「日本ガイシ」は海外10ヵ国に17の生産拠点を有しているそうですが、サンギランの工場はその中でも最初に出来た海外生産拠点だそうです。製造しているのは自動車排気ガスを浄化するための「ハニセラム」という触媒担体で、販売先は触媒そのものを製造している企業です。これを次の工程で排気管中央の膨らんだ部分の内部に取り付け、最終的に排気管部品となって自動車製造会社のもとに届くという流れです。セラミック製品である「ハニセラム」の外観は円柱形のトイレット・ペーパーのような形ですが、横断面には蜂の巣のように極く微小な穴が無数に(1万個以上?)空いており、その穴の壁面(厚さは0.05mm)に触媒を塗ると、排気ガスが通過した時に化学反応が起こり、有害なガスが無害化されるという仕組みです。トイレット・ペーバーのサイズの「ハニセラム」の場合、穴の壁面の総面積はサッカー・グラウンド2面分に及ぶそうですから驚きです。正規の従業員は日本人7名を含めると263人で、ベルギーは労働コストが高いので機械化がかなり進んでいるとのことでした。
また、先日、ホンダ技研工業のゲント工場(「よもやま話」第5回ご参照)の操業35周年を記念する式典に招かれました。ホンダがベルギーに最初に進出したのは1962年で、場所はゲント市とブリュッセルの中間に位置するアルスト市。ゲント工場の設立はその16年後で、現在は欧州における部品配送のハブになっています。式典ではホンダが開発している人型ロボットのアシモ君が大活躍しました。アシモ君は技術の革新が進み、今では時速9kmの速さで歩行することや斜面歩行が出来、ペット・ボトルのキャップを抜いて液体を注ぐような動作も可能だそうです。自動車会社による人型ロボットの開発というのは面白いアイデアですね・・・。
<大使公邸で開催した2つのミニ・コンサート>

 最近、大使公邸において2回続けてクラシック音楽のミニ・コンサートを開催し、招待客に大変喜んでいただきました。1回目は「テ・ド・ラミチエ」というベルギー婦人の親日団体のメンバーらをお招きして、ブリュッセルの音楽学校に留学している日本人の女子学生3人による演奏を聴いていただきました。バイオリン、ピアノ、声楽の組み合わせで、ホーム・コンサートらしく出演者と聴衆の距離が近く、大会場で聞く音楽とは一味違うところを満喫してもらえたと思います。2回目は3日前のことで、こちらではショパンのピアノ曲をベルギー人のユージェーヌ・イザイ(1858-1931)が編曲した楽譜の初演が行われました。。 最近、大使公邸において2回続けてクラシック音楽のミニ・コンサートを開催し、招待客に大変喜んでいただきました。1回目は「テ・ド・ラミチエ」というベルギー婦人の親日団体のメンバーらをお招きして、ブリュッセルの音楽学校に留学している日本人の女子学生3人による演奏を聴いていただきました。バイオリン、ピアノ、声楽の組み合わせで、ホーム・コンサートらしく出演者と聴衆の距離が近く、大会場で聞く音楽とは一味違うところを満喫してもらえたと思います。2回目は3日前のことで、こちらではショパンのピアノ曲をベルギー人のユージェーヌ・イザイ(1858-1931)が編曲した楽譜の初演が行われました。。

 この譜面はピアニストの永田郁代さんが米国で発見したようで、昨年のエリザベート・コンクールで2位になったヴァイオリニストの成田達輝さんに演奏(永田さん御自身が伴奏)してもらいました(この演奏会の模様は翌日のNHKニュースで報道されましたので、日本におられる方にも一部だけ鑑賞いただけたようです)。ユージェーヌ・イザイはエリザベート・コンクールと深い関わりを有する音楽家ですので、この夜のコンサートにもベルギー人の音楽愛好家に加え、同コンクールの関係者やイザイ氏の御子孫に当たる方々をお招きしました。クラシック音楽を通じてベルギーと日本が結ばれるのは嬉しい限りです。 この譜面はピアニストの永田郁代さんが米国で発見したようで、昨年のエリザベート・コンクールで2位になったヴァイオリニストの成田達輝さんに演奏(永田さん御自身が伴奏)してもらいました(この演奏会の模様は翌日のNHKニュースで報道されましたので、日本におられる方にも一部だけ鑑賞いただけたようです)。ユージェーヌ・イザイはエリザベート・コンクールと深い関わりを有する音楽家ですので、この夜のコンサートにもベルギー人の音楽愛好家に加え、同コンクールの関係者やイザイ氏の御子孫に当たる方々をお招きしました。クラシック音楽を通じてベルギーと日本が結ばれるのは嬉しい限りです。
<ナミュール大学で上映した日本映画と私の講演>
 2週間近く前にナミュール大学(ブリュッセルの南東65kmに所在)で「サムライの時代から現代日本へ」というテーマで1時間ほど講演をしました。講演の前には藤沢周平の小説を中西健二監督が映画化した「花のあと」(2010年)を上映し、それを受ける形で私から日本の近代史についてお話をしたのです。私自身、藤沢周平の時代小説は好きで、それらを映画化した作品はほとんど見ています。特に、「たそがれ清兵衛」や「武士の一分」は大好きな映画で、外国の日本映画ファンには是非とも見て欲しい作品ですね。幕末の東北武士の貧しい生活とその中でサムライとしての矜持を持って清く正しく生きる姿は感動的で、現代の日本人が失ってしまった倫理観の厳しさを思い起こさせます。私は、昔、米国のシカゴで総領事をしていた頃に「たそがれ清兵衛」を米国人に見てもらったことがあるのですが、実は余り受けませんでした。幕末という時代背景や東北という土地柄を理解していないと、藤沢作品の良さは分かりにくいのかも知れません。それと、米国の若者にとってサムライの映画はニンジャが登場するハリウッド的なアクション物でないと面白味に欠けるようです。では、ベルギー人はどうであったかというと、反応はまちまちで、やはり理解し難かったように見受けました。サムライの人生観や美学は特殊なのかも知れませんね・・・。 2週間近く前にナミュール大学(ブリュッセルの南東65kmに所在)で「サムライの時代から現代日本へ」というテーマで1時間ほど講演をしました。講演の前には藤沢周平の小説を中西健二監督が映画化した「花のあと」(2010年)を上映し、それを受ける形で私から日本の近代史についてお話をしたのです。私自身、藤沢周平の時代小説は好きで、それらを映画化した作品はほとんど見ています。特に、「たそがれ清兵衛」や「武士の一分」は大好きな映画で、外国の日本映画ファンには是非とも見て欲しい作品ですね。幕末の東北武士の貧しい生活とその中でサムライとしての矜持を持って清く正しく生きる姿は感動的で、現代の日本人が失ってしまった倫理観の厳しさを思い起こさせます。私は、昔、米国のシカゴで総領事をしていた頃に「たそがれ清兵衛」を米国人に見てもらったことがあるのですが、実は余り受けませんでした。幕末という時代背景や東北という土地柄を理解していないと、藤沢作品の良さは分かりにくいのかも知れません。それと、米国の若者にとってサムライの映画はニンジャが登場するハリウッド的なアクション物でないと面白味に欠けるようです。では、ベルギー人はどうであったかというと、反応はまちまちで、やはり理解し難かったように見受けました。サムライの人生観や美学は特殊なのかも知れませんね・・・。
<ブリュッセル駅伝の号砲>
 先の週末、ブリュッセル市内で開催されたアマチュア駅伝大会に来賓として招待され、ベルギーのオリンピック金メダリスト(2008年北京オリンピック・女子走り高跳び)のティア・エルボーさんと共にスタートの号砲を鳴らす役を務めました。この大会は「アセルタ」というベルギー企業が主催しており、参加チーム1260、ランナーの総数が7560人という世界最大規模の駅伝大会です。各チームは6人で構成され、それぞれが決められた距離を走り、合計で42.195kmを走破するというものです。我が大使館員も日本政府機関の駐在員らと1チームを結成して参加してくれました。私と主催企業のデパープ社長とは、ある偶然から知り合ったのですが、企業経営・社員教育のコンサルタント業を営む同社長から「日本で生まれたエキデンこそ、社員間の絆を強くする最適のスポーツ」という言葉を聞き嬉しくなりました。 先の週末、ブリュッセル市内で開催されたアマチュア駅伝大会に来賓として招待され、ベルギーのオリンピック金メダリスト(2008年北京オリンピック・女子走り高跳び)のティア・エルボーさんと共にスタートの号砲を鳴らす役を務めました。この大会は「アセルタ」というベルギー企業が主催しており、参加チーム1260、ランナーの総数が7560人という世界最大規模の駅伝大会です。各チームは6人で構成され、それぞれが決められた距離を走り、合計で42.195kmを走破するというものです。我が大使館員も日本政府機関の駐在員らと1チームを結成して参加してくれました。私と主催企業のデパープ社長とは、ある偶然から知り合ったのですが、企業経営・社員教育のコンサルタント業を営む同社長から「日本で生まれたエキデンこそ、社員間の絆を強くする最適のスポーツ」という言葉を聞き嬉しくなりました。
<サン・ミッシェル大聖堂で聞くホセ・ヴァン=ダム>
 10日ほど前、ブリュッセル中心部にあるサン・ミッシェル大聖堂においてベルドナー・コンサートが催され、ベルギーに来て初めて世界的なオペラ歌手であるホセ・ヴァン=ダムの生の歌唱を聴きました。現在、73歳の高齢におなりですが、バス・バリトン歌手としての低音の魅力は未だ衰え知らず、という感じでした。このコンサートは、臓器提供を啓蒙するチャリティ・コンサートで、ベルギー政府(保健省)が主催したものです。オーケストラはブリュッセル・アンサンブル・オーケストラという若手演奏家によって構成された楽団。男女2人のオペラ歌手が10曲以上の歌曲を交互に歌ってくれたのですが、男性歌手は勿論ホセ・ヴァン=ダム、そして女性の方は何と日本人の筬田美弥城(おさだみやぎ)さんというメゾ・ソプラノ歌手です。筬田さんはベルギーに在住する歌手で、過去20年近くヨーロッパを中心に活躍しておられるようですが、私はこの日まで全く存じ上げませんでした。ホセ・ヴァン=ダムとは共演する機会も多いようで、オペラ・ファンにとっては良く知られた方のようです。経歴書によれば、ベルギーの音楽学校で声楽の先生もしているとのことです。ベルギーに在住する日本人の女性オペラ歌手と言えば、ブリュッセルのコンセルヴァトワールで教鞭をとっておられる正木裕子先生を存じ上げていますが、他にも田口智子さんなど何人かオペラ界で活躍している日本人女性がいるようです。日本人の場合、男性より女性の方が国際性が高いのかも知れませんね・・・。 10日ほど前、ブリュッセル中心部にあるサン・ミッシェル大聖堂においてベルドナー・コンサートが催され、ベルギーに来て初めて世界的なオペラ歌手であるホセ・ヴァン=ダムの生の歌唱を聴きました。現在、73歳の高齢におなりですが、バス・バリトン歌手としての低音の魅力は未だ衰え知らず、という感じでした。このコンサートは、臓器提供を啓蒙するチャリティ・コンサートで、ベルギー政府(保健省)が主催したものです。オーケストラはブリュッセル・アンサンブル・オーケストラという若手演奏家によって構成された楽団。男女2人のオペラ歌手が10曲以上の歌曲を交互に歌ってくれたのですが、男性歌手は勿論ホセ・ヴァン=ダム、そして女性の方は何と日本人の筬田美弥城(おさだみやぎ)さんというメゾ・ソプラノ歌手です。筬田さんはベルギーに在住する歌手で、過去20年近くヨーロッパを中心に活躍しておられるようですが、私はこの日まで全く存じ上げませんでした。ホセ・ヴァン=ダムとは共演する機会も多いようで、オペラ・ファンにとっては良く知られた方のようです。経歴書によれば、ベルギーの音楽学校で声楽の先生もしているとのことです。ベルギーに在住する日本人の女性オペラ歌手と言えば、ブリュッセルのコンセルヴァトワールで教鞭をとっておられる正木裕子先生を存じ上げていますが、他にも田口智子さんなど何人かオペラ界で活躍している日本人女性がいるようです。日本人の場合、男性より女性の方が国際性が高いのかも知れませんね・・・。
|