|
第28回 ベルギーは既に秋の気配
2013年9月2日
ついに昨日のブリュッセルの最高気温は20℃を下回り、最低気温は10℃だったようです。郊外の森の木々にも紅葉の気配が漂い、東京ならすっかり秋といった様相です。ベルギーの人たちに言わせると「今年の夏は異常」だったようで、7月を中心に快晴の日々が続きました。私は36-37年前にベルギーに在勤しておりましたが、夏の気候がこれほど快適だった記憶はありません。これならわざわざ南仏や地中海地方にヴァカンスに出かける必要はありませんね。昨冬が異常な悪天候だったことを思うと全くウソのような好天です。
ブリュッセルは緯度で見ると極東の樺太(カラフト)あたりに位置するため、7月は朝5時半頃に日の出となり、日没は何と夜の10時過ぎです。ところが、8月も後半に入ると一気に日が短くなり、朝は7時を過ぎないと日が昇らず、陽が沈むのは夜の8時半頃になります。日照時間が1ヵ月半で3時間以上短くなる感じです。真冬になれば日の出は午前9時、日没は午後4時半頃になりますから一日の3分の2が夜になってしまいます。秋の気配と共に気持ちは既に憂鬱になり始めています。
<日本とベルギーとの外交交流>
日本とベルギーとの間には特段の外交上の懸案はなく、その意味では良好な関係を有していると言えるのですが、政治レベルでの交流は必ずしも活発とは言えません。そうした中で、先週、松山政司・外務副大臣(参議院議員)がブリュッセルにお出でになり、レンデルス外務大臣(副首相)と会談いただいたのは両国外交当局間の連携を深める良い機会となりました。両者は、二国間の経済関係を発展させる方策について突っ込んだ意見交換をされた他、東アジアからアフリカ・中東に至る国際情勢についても意見を交わしました。また、松山副大臣はデ・デッケル上院副議長(国務大臣)にもお会いし、上院の本会議場をご案内いただいた他、議員交流などについて有意義な意見交換をされました。デ・デッケル副議長は14年前に上院議長として日本を公式訪問しており、その折に天皇陛下に拝謁する機会を得たことを大変良い思い出として語ってくれました。更に、松山副大臣は前日の夜にベルギーに進出している日本企業の関係者とも懇談し、ベルギーにおける企業活動の現状について説明を受けました。なお、10日前には外務大臣政務官の阿部俊子衆議院議員が当地に立ち寄られ、来週は、衆議院の決算行政監視委員会の一行が来訪してベルギー連邦議会の関係者と意見交換することが予定されています。こうした形で政治レベル・議員間の交流が進むことは大使としても嬉しいことです
<日本を訪れたベルギーからの高校生>
 3日前、インターナショナル・スクール(ISB)の生徒や先生方20人ほどを大使公邸にお招きして懇談しました。ISBは、昨年、東日本大震災を受けた被災者支援活動の一環として宮城県の高校生30人ほどをベルギーに招待しており、今年は、自校の高校生16名を去る7月末から8月にかけて3週間近く訪日させ交流を深めています。今回はこの生徒たちと引率の先生方、そして交流活動の実現にかかわられた関係者を招いて、被災地の高校生たちとの交流状況や気仙沼など各訪問先の印象について伺いました。名古屋ではちょうど大相撲が場所中だったようで横綱の白鳳関に面会したことを懐かしそうに語ってくれました。京都の仁和寺に2泊滞在したことも良い思い出になっているようです。ただ、やはり最も強い印象が残っているのは気仙沼でホストファミリーと一緒に過ごした日々であり、津波被害の爪痕を残している海岸沿いの風景であるとのことでした。「来年も日本に行きたいですか」と尋ねると、ほとんど全員が「はい」と答えてくれたのは嬉しい限りですね。 3日前、インターナショナル・スクール(ISB)の生徒や先生方20人ほどを大使公邸にお招きして懇談しました。ISBは、昨年、東日本大震災を受けた被災者支援活動の一環として宮城県の高校生30人ほどをベルギーに招待しており、今年は、自校の高校生16名を去る7月末から8月にかけて3週間近く訪日させ交流を深めています。今回はこの生徒たちと引率の先生方、そして交流活動の実現にかかわられた関係者を招いて、被災地の高校生たちとの交流状況や気仙沼など各訪問先の印象について伺いました。名古屋ではちょうど大相撲が場所中だったようで横綱の白鳳関に面会したことを懐かしそうに語ってくれました。京都の仁和寺に2泊滞在したことも良い思い出になっているようです。ただ、やはり最も強い印象が残っているのは気仙沼でホストファミリーと一緒に過ごした日々であり、津波被害の爪痕を残している海岸沿いの風景であるとのことでした。「来年も日本に行きたいですか」と尋ねると、ほとんど全員が「はい」と答えてくれたのは嬉しい限りですね。
<ベルギーの原子力研究所と福島大学>
 先週、ブリュッセル市内で、ベルギー原子力研究所(SCK・CEN)と福島大学との間で研究協力に関する覚書の署名式が行われました。ベルギー側は一昨年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故後、この事故が生態系に及ぼす影響などについて共同で研究することを提案して来ており、今回、福島大学から高橋副学長らがベルギーを訪れた機会に協力覚書が署名されることになりました。もともと、ベルギー原子力研究所はCOMETと呼ばれる全ヨーロッパを巻き込んだ放射線生態学に関する協力事業を推進しており、実質的には福島大学がこれに参加するような形になりそうです。また、「よもやま話」(第17回)で紹介したように、ベルギーの研究所は放射性廃棄物の管理に関して先端的な研究を推進しており、この分野でも福島大学との協力が進むことが期待されています。なお、福島大学の一行の中に三味線の名手がおり、上述の署名式後のミニ・パーティの折に演奏してくれました。おかげで和気藹々とした式典になったのはとても良かったと思います。 先週、ブリュッセル市内で、ベルギー原子力研究所(SCK・CEN)と福島大学との間で研究協力に関する覚書の署名式が行われました。ベルギー側は一昨年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故後、この事故が生態系に及ぼす影響などについて共同で研究することを提案して来ており、今回、福島大学から高橋副学長らがベルギーを訪れた機会に協力覚書が署名されることになりました。もともと、ベルギー原子力研究所はCOMETと呼ばれる全ヨーロッパを巻き込んだ放射線生態学に関する協力事業を推進しており、実質的には福島大学がこれに参加するような形になりそうです。また、「よもやま話」(第17回)で紹介したように、ベルギーの研究所は放射性廃棄物の管理に関して先端的な研究を推進しており、この分野でも福島大学との協力が進むことが期待されています。なお、福島大学の一行の中に三味線の名手がおり、上述の署名式後のミニ・パーティの折に演奏してくれました。おかげで和気藹々とした式典になったのはとても良かったと思います。
<名古屋港とベルギーの2つの港>
 アントワープ港及びゼーブリュージュ港が日本の名古屋港と交流を深めていることは以前に紹介しました(「よもやま話」第23回)が、先日、その名古屋港の関係者一行(32名)がベルギーを訪問されました。アントワープ港とは25年に亘る姉妹関係があり、今回はこれを記念する式典が行われました。また、一行は、ブリュッセル市内の会場でベルギー側の港湾関係者を招いたレセプションを開催し、名古屋港の利用促進をPRするイベントを行いました。先月、名古屋港はゼーブリュージュ港とパートナーシップ関係を築いたばかりであり、日本とベルギーが港湾関係を通じて協力を深めていることは嬉しい限りです。名古屋港は取扱い貨物の量と貿易額で日本一の港であり、自動車の輸出基地としての役割を中心に海外の主要な港と緊密な関係を有しています。アントワープ港の敷地内で行われた式典の際、建設途上のドゥールガンク・ドックを参加者全員で視察する機会がありました。アントワープ港では4つ目となる巨大な水門が既に姿を見せつつあり、500mを超える深水ドックと共に2016年初めの完成が見込まれているようです。これが完成する暁にはアントワープ港はヨーロッパ第一の港になると期待されています。 アントワープ港及びゼーブリュージュ港が日本の名古屋港と交流を深めていることは以前に紹介しました(「よもやま話」第23回)が、先日、その名古屋港の関係者一行(32名)がベルギーを訪問されました。アントワープ港とは25年に亘る姉妹関係があり、今回はこれを記念する式典が行われました。また、一行は、ブリュッセル市内の会場でベルギー側の港湾関係者を招いたレセプションを開催し、名古屋港の利用促進をPRするイベントを行いました。先月、名古屋港はゼーブリュージュ港とパートナーシップ関係を築いたばかりであり、日本とベルギーが港湾関係を通じて協力を深めていることは嬉しい限りです。名古屋港は取扱い貨物の量と貿易額で日本一の港であり、自動車の輸出基地としての役割を中心に海外の主要な港と緊密な関係を有しています。アントワープ港の敷地内で行われた式典の際、建設途上のドゥールガンク・ドックを参加者全員で視察する機会がありました。アントワープ港では4つ目となる巨大な水門が既に姿を見せつつあり、500mを超える深水ドックと共に2016年初めの完成が見込まれているようです。これが完成する暁にはアントワープ港はヨーロッパ第一の港になると期待されています。
<隣家の老婦人の葬儀>
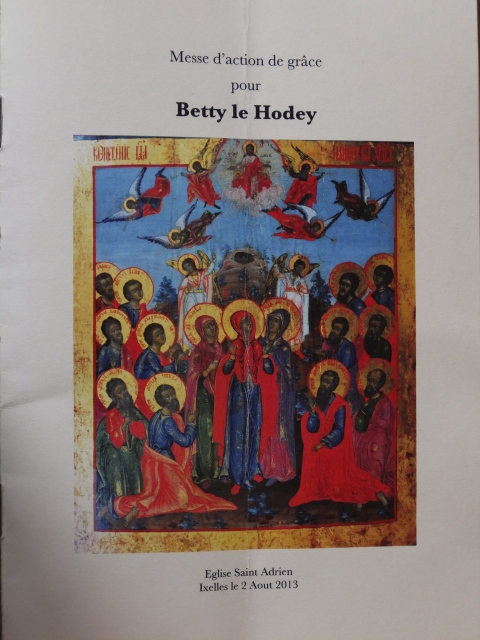 先月、ブリュッセルのイクセル地区にある日本大使公邸の隣に住んでおられた老婦人が93歳でお亡くなりになり、近所の教会で葬儀が執り行われました。親類縁者や友人・知人ら400人近くが参列した大変立派な葬儀でした。私にとっては、単に隣人というだけでなく、大使公邸の元家主の姉君に当たる女性であり、また、ブリュッセル着任後に面識を得た地元新聞社オーナーの御母堂でもあります。この女性の名前は、エリザベート・ル・オデさん。彼女は第二次世界大戦後のベルギーにおいて実業家として活躍し、後に政治家になります。女性の社会的地位の向上に努め、所属する政党内に女性局を設けて、その初代局長にも就任したそうです。また、敬虔なカトリック教徒であった彼女は、女性のスカウト運動を創始し、職場への女性進出にも指導的役割を果たしています。8人の子供を育てた後、46歳の時にご主人を亡くし、寡婦となってなお社会的に活躍した人生は誠に立派なものだったと思います。葬儀には6人のお子様方(と言っても御長男は68歳ですが)をはじめ孫、ひ孫の世代まで総勢89人の直系の御遺族が参列しており、カトリックの古式に則った2時間半近いミサは、私にとっては大変印象的でした。地元の新聞は大きな追悼記事を掲載し、6年前に当時のアルベール2世国王陛下から国家への貢献が認められ男爵の爵位を授与された折の写真を添えておりました。彼女は、第二次世界大戦で荒廃したベルギーを再建した世代の中心にいた女性の一人だったのだと思います。 先月、ブリュッセルのイクセル地区にある日本大使公邸の隣に住んでおられた老婦人が93歳でお亡くなりになり、近所の教会で葬儀が執り行われました。親類縁者や友人・知人ら400人近くが参列した大変立派な葬儀でした。私にとっては、単に隣人というだけでなく、大使公邸の元家主の姉君に当たる女性であり、また、ブリュッセル着任後に面識を得た地元新聞社オーナーの御母堂でもあります。この女性の名前は、エリザベート・ル・オデさん。彼女は第二次世界大戦後のベルギーにおいて実業家として活躍し、後に政治家になります。女性の社会的地位の向上に努め、所属する政党内に女性局を設けて、その初代局長にも就任したそうです。また、敬虔なカトリック教徒であった彼女は、女性のスカウト運動を創始し、職場への女性進出にも指導的役割を果たしています。8人の子供を育てた後、46歳の時にご主人を亡くし、寡婦となってなお社会的に活躍した人生は誠に立派なものだったと思います。葬儀には6人のお子様方(と言っても御長男は68歳ですが)をはじめ孫、ひ孫の世代まで総勢89人の直系の御遺族が参列しており、カトリックの古式に則った2時間半近いミサは、私にとっては大変印象的でした。地元の新聞は大きな追悼記事を掲載し、6年前に当時のアルベール2世国王陛下から国家への貢献が認められ男爵の爵位を授与された折の写真を添えておりました。彼女は、第二次世界大戦で荒廃したベルギーを再建した世代の中心にいた女性の一人だったのだと思います。
<36年振りの自動車レース>
 先週の日曜日、ブリュッセルの南東140kmのところにあるスパ・フランコルシャン自動車レース場で、フォーミュラ・ワンのレースがあり、ワロン地域(フランス語圏)政府の招待を受けて観戦して来ました。私自身は前回のベルギー勤務時代にもこのレースを見たことがあり、今回は実に36年振りということになります。「ベルギー・グランプリ」と呼ばれるこのレースが開催されるのは今年が46回目だそうですが、ベルギーにおける自動車レースの歴史は古く、何と1925年にはナショナル・グランプリのレースが始まっているようです。当時は、ベルギー・ブランドの自動車が生産されていた時代で、第二次世界大戦後の国際競争の中で自国の自動車産業が消滅しても、「ベルギー・グランプリ」は毎年立派に開催され続けています。今回のレースには日本の自動車メーカーの車の出走はなく、日本人レーサーも出場しておりませんが、いくつかの日本企業がスポンサーとして後援しているようです。スパ・フランコルシャンの自動車レース場は一周が7kmで、レースではこれを44周(合計308km)して順位を競います。ちょうどブリュッセル・パリ間の距離を走る感じですね。1周の平均時速は約200km、最高時速は300kmを超えているようで、耳をつんざくような爆音と共に目の前を瞬時に走りすぎていくレーシング・カーの迫力は満点です。こうしたレースの観戦は日常のストレスを解消する上でとても有効ですね・・・。 先週の日曜日、ブリュッセルの南東140kmのところにあるスパ・フランコルシャン自動車レース場で、フォーミュラ・ワンのレースがあり、ワロン地域(フランス語圏)政府の招待を受けて観戦して来ました。私自身は前回のベルギー勤務時代にもこのレースを見たことがあり、今回は実に36年振りということになります。「ベルギー・グランプリ」と呼ばれるこのレースが開催されるのは今年が46回目だそうですが、ベルギーにおける自動車レースの歴史は古く、何と1925年にはナショナル・グランプリのレースが始まっているようです。当時は、ベルギー・ブランドの自動車が生産されていた時代で、第二次世界大戦後の国際競争の中で自国の自動車産業が消滅しても、「ベルギー・グランプリ」は毎年立派に開催され続けています。今回のレースには日本の自動車メーカーの車の出走はなく、日本人レーサーも出場しておりませんが、いくつかの日本企業がスポンサーとして後援しているようです。スパ・フランコルシャンの自動車レース場は一周が7kmで、レースではこれを44周(合計308km)して順位を競います。ちょうどブリュッセル・パリ間の距離を走る感じですね。1周の平均時速は約200km、最高時速は300kmを超えているようで、耳をつんざくような爆音と共に目の前を瞬時に走りすぎていくレーシング・カーの迫力は満点です。こうしたレースの観戦は日常のストレスを解消する上でとても有効ですね・・・。
| 